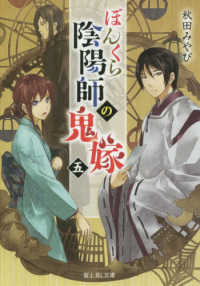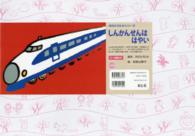内容説明
紀元前5世紀、アケメネス朝ペルシアが西インドからエジプトに跨る大帝国を築いた時、国内で唯一共用する言語はペルシア語でなく、アラム語であったということは興味深いものがある。時代が下がって、キリスト自身の言葉もヘブライ語の多いアラム語であったという。そこで、中近東の言語がイスラムの影響でアラビア語に変わった後も、キリスト教会の内部で細々とではあるが、現代までもアラム語は使用され続けているのである。多くの文献からこれらアラム語群を比較・検証しようとしたのが本書の目的である。
目次
1 オリエントの対立抗争(メソポタミア;エラム高原 ほか)
2 アラム語の歴史(概説;アラム文字 ほか)
3 文法(セム語族比較文法;シリア語文法)
4 実例の紹介(アラム文献;パレスチナ文献 ほか)
5 グローサリー
著者等紹介
飯島紀[イイジマオサム]
1928年東京都目黒区出生。1953年(旧制)京都大学理学部卒業。同文学部にてセム語等履修。1988年松下電器産業(株)退職。現在日本オリエント学会会員。著書に「アッカド語」~楔形文字と文法~(国際語学社2000年7月発行)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
びっぐすとん
16
図書館本。『アッカド語』に続き、キリストが喋っていたというアラム語を借りてみた。公用語として広範囲で話され、派生した言語も多く、様々な文字で書き表された言語らしい。現代アラム語もあって話者がいることにも驚き。英会話の先生が「日本語の文字を覚えられない」とぼやいていたが、その気持ちが分かる。字体が違いすぎるし、右→左の横書読みも目が疲れる。これらを全部読める研究者を尊敬する。解読された手紙の内容は今と変わらないビジネス文書や法律文書など。日本語の「益々ご清祥のこととお慶び申し上げます」みたいな定型文もある。2020/07/04
-

- 和書
- 墨攻 〈1〉 小学館文庫