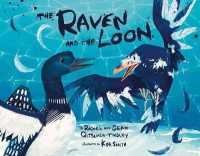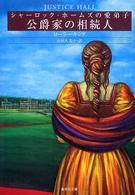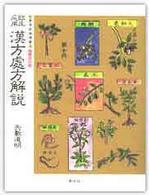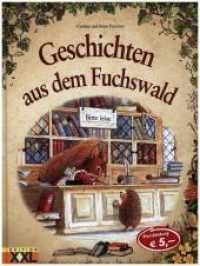内容説明
精読が身につけば読書の質は飛躍的に高まる!精読で読書の基礎体力をつけませんか?精読の理論と実践を紹介するありそうでなかった読書指南書です。
目次
第1部 読書とは何か(本の読み方のいろいろ―精読のすすめ;読書とは何か ほか)
第2部 基礎編 文を読む(ダイ・ドドナ・ドドナの読み取り;文の区切り方―「首」と「くさび」 ほか)
第3部 応用編 文章を読む(日本国憲法「前文」を読む―文構造の読み取り;文章表現の読み取り―「ニュースピーク」の原理 ほか)
第4部 読書の「道具箱」(読書のための印つけのポイント;ページへの印つけ ほか)
著者等紹介
渡辺知明[ワタナベトモアキ]
コトバ表現研究者。1952年、群馬県桐生市生まれ。法政大学卒業後、日本コトバの会に入会、以来、「読む・書く」「話す・聞く」の実践研究と実技指導を続ける。現在、コトバ表現研究所所長、日本コトバの会講師・事務局長、表現よみオーの会代表(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かおりん
20
本の読み方は三読法。通読、精読、味読。読書の方法や技術について掘り下げてある。多読、速読はどうしても雑な読み方になる。多量の本を読み流して内容の薄い知識を寄せ集めているの言葉にドキッとした。読書の質をあげるのが精読。文、文節、要素など奥が深い。本に印つけと書き込みをするなんて学生の時と受験の時ぐらいだったな。たまには音読もしてみようと思った。2020/02/27
Nazolove
18
改めて、読書とはなんぞや?というテーマに読んでみた作品。 そういえばいままでなんとなく読んでなんとなく感想書いて…っていうのを延々くりかえしてたから、こうやって一冊の本と対話するように読んでみる、なんてことをすっかり忘れていたかなと改めて思った。 段々高校の現代文みたいな話を聞いてる印象を受けたけど、真に本好き、本読みであるならばこれくらいのことを)るべきなのかななんて思ってしまった。(時間ある人にしか出来ないことかもしれないけど) これからは私もこの本くらいのことを実践していこうと思った。2019/07/04
masabi
10
【概要】本を正確に読み味わうための精読を解説する。【感想】一文を節で分け、接続語他に印をつけ、と懇切丁寧に精読の方法について書かれているのだが、受験でもここまでやらないと思うほど細かい。自分の読み方を点検する良い機会になった。読書メモはともかく自作の索引は作りたいと思いつつできていないので、機会なり本なりを見つけてやってみたい。文章を味わう、理解するために音読が取り上げられており、これは盲点だった。2023/10/24
じゃくお
2
精読が重要であることは勿論ですが、本書の精読はやりすぎな印象。これでは現代文解釈と同じようなものです。私は感覚主義なので論理的で人を納得させ得る考えを論ずることはできませんが、芸術の一分野である文学をこのような読み方で読むことは私の感覚が拒否します。しかし、読解能力の足りない人が難解な文章を理解するために‶超”精読を行うことは推奨してもよい行為かもしれません。「コトバ」に関わる方が「他力本願」を誤った意味(悪い意味)で用いることは如何なものか。よく行われることですが、この誤用に出会う度に不快になります。2019/10/31
パン屋
1
本の読み方を懇切丁寧に教えてくれる本。 指を当てて読む、それだけでもかなり読むスピード上がるんだと発見!この本にも書いてあったが、つまらない本に遭遇してしまった時は流し読みで良いらしい。そりゃそうだよね。 『よい書物を読むことによって、自身の精神が形成される。』 ★★★☆☆2025/06/14