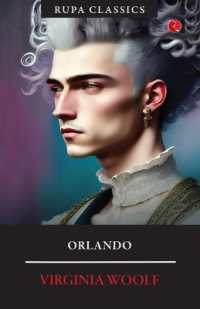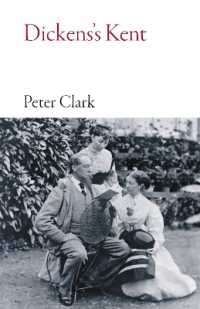内容説明
殺されてたまるか!就活でだまされないための理論武装。幻想まみれの「意識高い系」就活よ、さようなら。暴力、いじめ、うつ、ドラッカー…働く現場から描き出す現代日本のリアル労働論。
目次
働く前から疲れないように
第1章 経営書・自己啓発本をつい読みたくなる人たちへ
第2章 職場における「いじめ」
第3章 労働と「うつ病」
第4章 労働と「死」
第5章 「品質」の作り込みの低下
第6章 「キャリア」ブームに煽られる人たちへ
第7章 「社会貢献」に惹かれる「良い人」たちへ
第8章 働くということを自分たちのものに取り戻す
働きだしてから自分が追い込まれないために、周りの者を追い込まないように
著者等紹介
伊原亮司[イハラリョウジ]
1972年生まれ。一橋大学商学部卒業。一橋大学大学院社会学研究科博士後期課程修了、社会学博士(2004年)。現在、岐阜大学地域科学部准教授。専攻、労働社会学、経営管理論、現代社会論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きいち
24
紹介されている職場での暴力やいじめの例も、うつに至る長時間労働の例も、実際に働くとほとんどの職場では対岸の火事としか感じられない。でも。「よい職場」にある働く意義や自律性、成長の機会、そして仲間といったポジティブなもの、それによって見えなくなっていても実は程度の差。ダークサイドの芽はどの職場にもある。だから、職場に適応し能力形成に励みながら、同時に知識と外での足場を持ち、納得できる労働社会像を模索していこう、という著者の提言は、働く個人にとって一番の戦略だろう。よい塩梅って難しいけれど、やってみなきゃね。2017/11/23
ドル子
2
図書館で。 トヨタのカイゼンの裏側や期間工の話、ゲイツ財団の活動の側面の話などは大変興味深かった。 どの企業も何もかもがうまくいっている訳ではない。違和感やしこりのようなものを抱えている。 きらきらキャリア本に書かれている内容だけを受け止めてしまうと、理想と現実の間で疲弊するので、こういう本があってもいいと思います。2015/06/19
田中峰和
2
タイトルから想像できる通り、著者は働かされる側寄り。「職場におけるいじめ」では、日産における多数派労働組合による少数派組合員へのいじめを紹介。経営を再生したのは10億円の報酬を得たゴーンではなく、合理化のしわ寄せを一身に受けた労働者が一番の貢献者と主張する著者。「品質の作り込みの低下」では、学者の著者自らが期間工労働者としてトヨタで3カ月半勤務して参与観察。期間が限定されている上に賃金も低い非正規労働者が無理やりQCサークルまで参加させられては、品質も低下するし、リコールも増えるだろうとの主張に納得。2015/04/04
あつもり
1
自らトヨタの期間従業員として働いてみた経験をもと、「最強の現場」の「綻び」を指摘した第5章が面白いです。トヨタも期間従業員への依存度が増える中、正規・非正規を「同等」に、「一体化」して扱うことにこだわっているように見えた(もちろん待遇格差はある)とのこと。「期間従業員がラインの半数を占めても、傍目からは深刻な問題は感じられない」「しかし、現場の内側に入って労働実態を見ると、必ずしも『うまくいっている』とは言えない」。それは「些細な現象」であるが、「トヨタの競争優位の根幹を揺るがしかねない」。(P.129)2021/02/21
Yutaro Tetsumi
0
働く前に読めてよかった。アカデミックに労働を問い直す。2015/10/11