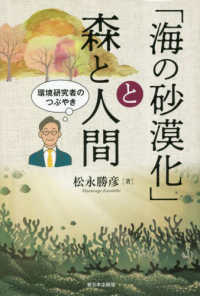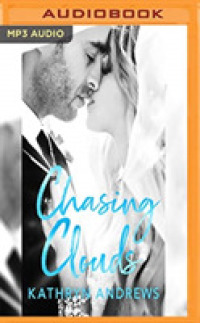目次
第1章 言語理論
第2章 意味づくりのリソース
第3章 社会意義活動と意味の具現化
第4章 マルチモダリティの方法論と理論的課題
第5章 体系機能理論を援用したマルチモーダルテクストの意味づくり
第6章 意味づくりを拡張する外国語・第二言語発達
第7章 日常の言語学
著者等紹介
照屋一博[テルヤカズヒロ]
言語学博士。ニューサウス・ウェールズ大学(シドニー)、理化学研究所脳科学総合研究センター言語知能研究チーム非常勤研究員、香港理工大学副教授Associate Professorを経て、現在、在野の言語学・日本語学研究者。専門は、体系機能言語理論・言語記述、語彙文法論、言語類型論、ディスコース分析、言語教育。オーストラリア、中国、日本、北米、南米、ヨーロッパ、中東など、世界各地で教授、講演をおこなう
奥泉香[オクイズミカオリ]
日本体育大学児童スポーツ教育学部教授。教育学博士(早稲田大学)。専門は国語科教育学、特に母語教育におけるマルチモーダル・リテラシー教育。全国大学国語教育学会2020年度優秀論文賞受賞。カメラ映像機器工業会(CIPA)との補助教材『遊ぼう!写真はことば』協働開発
マティスン,クリスチャン[マティスン,クリスチャン] [Matthiessen,Christian M.I.M.]
言語学博士。湖南大学、北京師範大学、およびオーストラリア国立大学特別栄誉教授。マッコーリー大学、そして香港理工大学講座教授Chair Professorを経て現職、マドリード・コンプルテンセ大学教授。体系機能言語学理論・言語記述の第一人者。研究分野は多岐にわたり、編著多数
ベイトマン,ジョン[ベイトマン,ジョン] [Bateman,John A.]
人工知能学博士。京都大学長尾真が率いる自然言語処理プロジェクトや南カリフォルニア大学情報科学研究所「PENMAN」自然言語処理プロジェクトに参画、ドイツ国立研究センター多言語処理プロジェクト「KOMET」の指揮などをへて、現在ブレーメン大学応用言語学教授。専門は、オントロジー、自然言語処理、マルチモダリティ、体系機能言語学
バーンズ,ハイジ[バーンズ,ハイジ] [Byrnes,Heidi]
言語学博士。ジョージタウン大学特別栄誉教授George M.Roth distinguished professor of Germanを経て、現在同大学名誉教授。米国応用言語学学会(AAAL)の会長、『現代言語誌』Modern Language Journalの編集主幹など多くの指導的役職を歴任。ドイツ語を対象とした言語カリキュラム内における上級言語リタラシーの発達を探求・解明した編著多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-
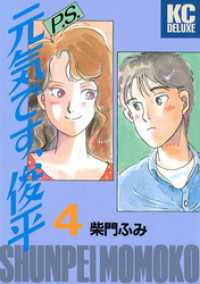
- 電子書籍
- P.S.元気です、俊平(4)