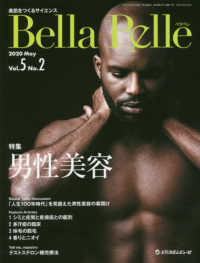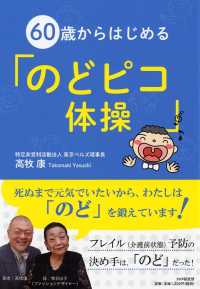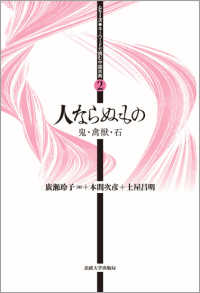- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 文化・民俗
- > 文化・民俗事情(日本)
内容説明
本書でいう「共同風呂」とは、主に農村地域において集落単位または集落内の何軒かの家が仲間を組織し、共同の浴場施設を設け。用水と燃料を調達して、湯沸し作業の交代制などの協力関係を維持しながら、仲間の家族全員が日常的に入浴したしくみをいい、いわゆる「もらい風呂」とは異なる。「銭湯(風呂屋)」に類似するが、毎回の入浴料を徴収しない、自主的な維持管理が行われる、入浴者が特定されている、などの相違点がある。また、湯沸し労働が必要であることから、温泉地の「共同浴場」とも違っている。その成立時期は、大正期を中心にその前後が多く、昭和40年代以降、高度経済成長の影響が庶民の暮らしに波及していくとともに、次第になくなっていった。本書は、あまり記録されることなく消えていった「共同風呂」の実態を発掘し、併せて、公衆浴場の事例や、韓国・中国の浴場に関する報告も含めて、入浴文化を考察する。
目次
1 共同風呂の特徴(共同風呂の意味;共同風呂の分布;成立と衰退;湯沸しについて;風呂の仲間;地域のなかの共同風呂)
2 共同風呂の事例研究(鳥取県中部の共同風呂;佐賀県旧北茂安町の共同風呂;愛媛県西部の共同風呂;北海道と沖縄県の共同風呂)
3 共同風呂の調査報告(秋田県と青森県の事例;新潟県と石川県における聞き書き;愛媛県西予市宇和町の座談会抄録;北部九州の市町村史から;長崎県における調査)
4 韓国の共同風呂(セマウル運動に伴う共同風呂;済州島における共同水浴び浴場)
5 いくつかの共同浴場事情(神戸と明石における公衆浴場の現状;三朝温泉と関金温泉の共同浴場;大阪府池田市の風呂と暮らし;韓国における沐浴湯の利用;東アジアの共同浴場;鳥取県中・西部における公共温泉の顧客圏)
著者等紹介
白石太良[シライシタロウ]
昭和12(1937)年4月13日生。大阪府出身。昭和40年3月、大阪市立大学大学院文学研究科(地理学専攻)修士課程修了。文学修士。大阪府立高等学校教諭、鹿児島女子短期大学教授を経て、昭和63年4月に流通科学大学開学に伴い同大学教授。図書館長、副学長を歴任。平成18年3月同大学を退職し、名誉教授となる。専門分野は人文地理学(とくに集落地理学・社会地理学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
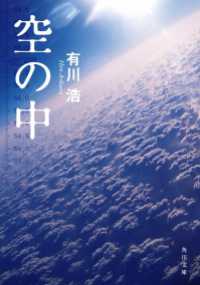
- 電子書籍
- 空の中 角川文庫