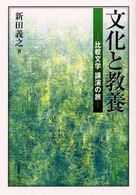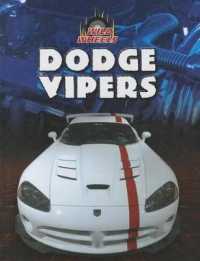出版社内容情報
ネットワークの発展により、ソフトウェア、音楽、書籍などの情報財が多く取り引きされている。情報財の特徴として、最初の一つを作るためのコスト以外は、生産するためのコストがほとんどかからないという点がある。本書は、情報財に基づくネットワーク上での市場の解析と、実践的なビジネス戦略にいかにして役立たせる方法が、分かりやすくまとめられた読み物である。
内容説明
インフォメーション製品(映画・音楽、ソフトウェア、株価など)は、今や工業製品に代わって世界のマーケットの主役となった。そして、今、多くの企業人たちが、この「新経済体系」に直面し、意思決定の指針となる有効な「新・経済学」を模索している。最先端のソフトウェア製品やWeb Magazineを市場に投入している経営者たちは、経済学の古典的な知恵を捨て去ろうとするが、その戦略策定の指針はトレンドを頼りに類推しているに過ぎない…。
目次
第1章 インフォメーション経済
第2章 インフォメーションの価格づけ
第3章 インフォメーションのバージョン化
第4章 権利の運用管理
第5章 ロックインを理解する
第6章 ロックインを管理する
第7章 ネットワークとプラスのフィードバック
第8章 協力と互換性
第9章 標準化戦争の戦い方
第10章 インフォメーション政策
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
110
最近サイバー経済・デジタル経済などこのような分野の本を読み直しています。この本は書かれたのは2000年前なのですが今読んでも古臭さはあまり感じません。アトム型産業からビット型産業へという副題が語るように、装置型産業から、IoTを利用した産業へということを先取りしているのかもしれません。それと、標準化への戦争というところで、結構オープン化が進むことへの対応ということも触れています。 いい本で何度か読みなおしたくなります。2017/01/02
takathy
2
万人にお勧めできる経済本。絶版になっているが大きな図書館に行けば見つかる(と思う)ので、何としてでも見つけて読んで欲しい。決して即効性のある本ではないが、何年か経った後に「あのとき読んでおいてよかった」と思える本だ。年に何度も再読すべし。ちなみに著者は現在Googleのチーフエコノミスト。2008/06/15
Yoshi
1
「レストラン経営者は誰でも一番売れるワインはメニューの中で二番目に安い品物だということをよく知っている」「ほとんどの買い手に対して既に固定した供給者がついているような相対的に成熟した市場では、決定を遅らせることが極めて有効な交渉術となる」「もう一つの先述は、非常によい条件を導入したパッケージに最もふさわしい顧客のタイプだと供給者に思わせること」「鎖はその最も弱い部分で全体の強さが決まる」など、個別具体的な戦術や考え方が豊富であり、中でも需用者側の外部性に係る記述は興味深かった。汎用性の高い事例満載の一冊。2015/11/29
Yukiko Yosuke
1
紹介して下さった先生がいい本だとおっしゃっていた通り、1999年に発刊されたとは思えない内容。ページ数が多くて読み切るのはちょっと大変ですが、読む価値あります。2012/06/20
ねぎとろ
1
最近の経済本10冊よりこの1冊。2007/03/13