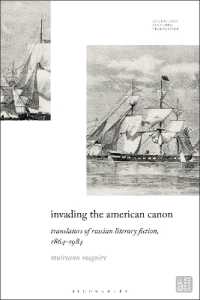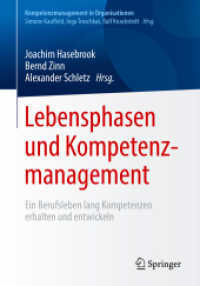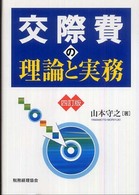内容説明
日本の気候風土の中で生き続ける伝統木造建築を読み解く。
目次
第1章 社と堂(社の建築;モヤ‐ヒサシの堂;和様の堂;大仏様と禅宗様の堂;中世の堂;近世の堂;その他の堂)
第2章 楼・閣・塔(鐘楼・鼓楼;楼門・二重門;楼閣・天閣;層塔;その他の塔)
第3章 農家と町家(農家建築の原型;上屋と下屋;農家建築の空間;町家建築の原型;町家建築の高層化;町家建築の空間)
著者等紹介
光井渉[ミツイワタル]
1963年広島県廿日市市生まれ。1987年東京大学工学部建築学科卒業。1989年東京大学大学院工学系研究科建築学専攻修士課程修了。1991年東京大学大学院工学系研究科建築学専攻博士課程中途退学。文化庁文化財保護部文部技官。1996年神戸芸術工科大学・環境デザイン学科専任講師(1999年より助教授)。1998年博士(工学)。2000年東京藝術大学・建築科助教授(2007年より准教授)。2014年東京藝術大学・建築科教授。2016年東京藝術大学副学長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
探建商会本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
G-dark
11
日本の伝統的な木造建築が持つ、特徴的な外観・内部空間・構法について知ろうという本。外観・内観の写真、平面図、断面図、詳細図が載っているので、細かい作りを学べます。日本ならではの気候、地震や台風といった災害にどう対応し、どう工夫が凝らされてきたかが伝わってきます。また、建築に使用する材料も、地域性やその時代背景が反映されているので、その当時の日本人がどう生き、何を必要としていたかが学べる気がします。しかも、どの建築物も機能的でありながら、何一つ無駄の無い研ぎ澄まされた美しさも兼ね備えているのが魅力!2019/11/04
chang_ume
8
軸組と小屋組が一致した「モヤーヒサシ構造」の古代建築から、平安期の天井採用を契機とした中世建築の野小屋形成および多重平面(正堂・礼堂構造)、その後の「軸組と小屋組の分離」を通じた近世建築の自由平面の成立が、一本筋の通った型式学的変遷の理解に見通しよい。当然、痕跡器官についても、モヤーヒサシ構造からの逸脱によって部屋の真ん中に入側柱が残った東福寺龍吟庵方丈の事例で確認できるとする。太田博太郎『奈良の寺々』、山岸常人『塔と仏堂の旅』と並んで、建築史基礎理解のベストブックだろう。2024/12/19
-
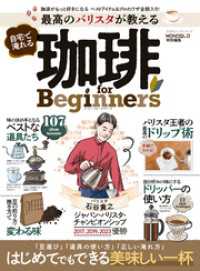
- 電子書籍
- 100%ムックシリーズ 最高のバリスタ…