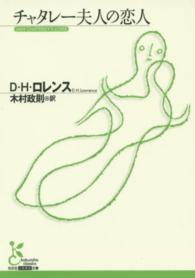出版社内容情報
本書は、建築家 隈研吾 が「建築は場所とつながっていなくてはならない」という哲学をていねいに「書き起こし」で解説している。
本書には、3・11の震災後の新しい建築哲学が盛り込まれています。
・ 隈研吾の代表作15事例と実験事例3例を、カラー写真と
図版で詳細に解説している。
・ 「場所」と「建築」の関係を歴史から徹底的に分析して、
教科書としてまとめている。
内容説明
ポスト震災の新しい建築哲学。18事例の素材・詳細を図解。
目次
悲劇が建築を転換する「生産」が建築を救う
収録事例(亀老山展望台―建築を消し、山を復元する;北上川運河交流館―環境保全と河川整備のためのトンネル型ミュージアム;水/ガラス―水平要素によって海と建築を接続する;森舞台 登米町伝統芸能伝承館―舞台を屋外化し、余白によって森と建築を接続する ほか)
実験プロジェクト事例(カサ・アンブレラ―フラードームをより軽く、よりゆるく;ウォーターブロック/ウォーターブランチ―細胞をヒントにした、遊牧・自律型建築システム;千鳥/GCプロソミュージアムリサーチセンター―飛騨高山の玩具をヒントにした、小断面の木造ユニットシステム)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
nobi
56
「場所」という視点からすると建築の歴史はこんなにも明快。リスボン大地震を契機に神に頼らぬ合理的建築が近代工業化と相まって抹殺した「場所」。3.11が露呈した「場所」を収奪された東北の現実。18の事例は現代でも「小さな場所(の材料、技術、職人を大事にすること)」の復活が可能であると物語っている。依頼主の石屋さんの二人の職人さんの手だけで建てた<石の美術館>。中世のシトー派修道院で使われた究極に透明なステンドグラスを再現使用した<銀山温泉藤屋>。<根津美術館>の表参道の喧騒から静かな場へと誘うアプローチ等々。2021/05/16
かっぱ
18
【図書館本】3.11後の建築について言及。現代の建築からは「場所」が失われてしまっているという。「大きな場所」から「小さな場所」へ。その場所で長年培われてきた人々の営みの中から、そこでの建築を見出す。その場所にしかない材料を使い、自然と違和感なく融合したような建築物がいい。自然光をどう取り入れるかに、とても工夫をされていて面白い。ガラスではなく石を薄くしたもので外の光が取り入れられるなんて知りませんでした。写真で実際の建築物の紹介多数あり。2014/04/21
nbhd
7
デリダが出てきます、僕にはとても気持ちいいのですが…。規範を与える「父」(=幾何学としての建築/普遍主義)でもなく、主観に立脚して規範を否定する子(=空間としての建築/主観主義)でもなく、あらゆるテクストを受容し、あらゆるテクストを生み出す能力をもった母なる建築、母なるコーラ(場)……と続きます。隈さんの本でいうと「小さな建築」と「自然な建築」を足した内容で①場所から生まれ、場所を失っていった建築史の概観、②現代思想を参照しつつ新たな建築理論の模索、③その模索と並走した実践の記録、の3部構成。2017/06/08
C-biscuit
5
建築なのは建築であるが、もはや哲学である。先の東日本大震災で考え方を含め人生感が変わったひとも多いと思うが、著者もその一人であるようだ。この本は教科書であり、若い人に向けたものである。そう思うと前半の建築史的な流れが知識となるのだろう。自分自身はのあたりが疎いので、後半のビジュアルたっぷりの18の事例が、写真も美しく、良かった。建築が好きな人は、こういうのを見て回るのも良いのだろう。自分も愛媛の亀老山展望台には行ってみたい気になる。写真は残念ながら曇っているようだが、晴れた日は景色も良いのだろう。2015/04/11
引用
2
『点・線・面』に向かって精度を上げていく名人芸の修行を見ている気分2022/05/03