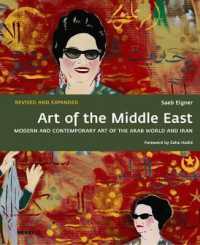内容説明
福岡城天守は四層ではなかったか。その絵図を紹介する。また、大友氏の家臣臼杵氏の筑前における重要性については意外に知られていない。名島城金箔瓦については再述した。前原の泉川と菅正利の意外な結びつきや松永家(森家)からみた博多の菓子歴史の一端も振り返ってみた。
目次
第1部 福岡城天守は四層(四重)か(海陵絵図に見る福岡城と天守閣;天守の変遷)
第2部 黒田二十四騎菅和泉正利と父(ふたつの名島城絵図;菅七郎兵衛正元の「天守之番衆」;南の丸二の曲輪(南二の丸)及び南三階櫓について
南二の丸南三階櫓と城代(城番)
菅七郎兵衛正元と菅和泉正利
新田干拓と開拓)
第3部 中世における筑前臼杵氏の動向について(博多古図;臼杵鑑続について;筑前臼杵氏と中世博多;「石城誌」の房州濠と石堂川)
第4部 続・五十二萬石如水庵(故松永初兵衛と松永勇基氏;松永勇基氏宅の菓子型(「庄」と「松」の焼印)
出来町集会所の土地登記名義
旧戸籍にみる松永家と森家系図
御笠川下流域の被差別部落
寛政の松原五人衆と松本治一郎)
第5部 九州の金箔瓦(名島城と金箔鯱瓦;日野江城(島原半島南有馬市)の金箔瓦
佐土原城(宮崎県)の金箔鯱瓦
史跡としての名島)
著者等紹介
荻野忠行[オギノタダユキ]
1939年生。九州大学文学部卒。歴史社会学研究。宮崎県立・福岡市立高校教諭。教頭。市教委高校担当主席指導主事。藤香会員。NPO福岡城市民の会員。福岡市在住(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。