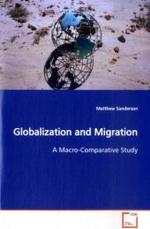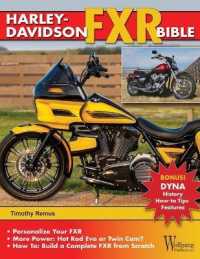- ホーム
- > 和書
- > エンターテイメント
- > アニメ系
- > アニメ研究本、マンガ論
内容説明
昭和43年、『少年ジャンプ』の創刊は黎明期の少年漫画の世界に新風を吹き込んだ。編集スタッフは、新人漫画家の才能を開花させ、次々にヒット漫画を生み出していった。本書は600万部という驚異的な部数を記録するまでに男たちが流した汗と涙、払った代償を赤裸々に描いたノン・フィクションである。
目次
第1章 苦戦の月刊誌時代
第2章 苦肉の新人起用策
第3章 ハレンチ学園&男一匹ガキ大将
第4章 漫画家専属制度
第5章 臨時労働者組合
第6章 新人漫画家パワー発進
第7章 発行記録への挑戦
第8章 宴のあと
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ようはん
5
2015年に亡くなった週刊少年ジャンプの第3代編集長である西村繁男氏が週刊少年ジャンプの創刊に至るまでの過程から草創期、編集長として全盛期の礎を築いた80年代頃までを回顧した内容。西村さんもそれなりにアクの強い人物であるが、その上司にあたるジャンプの初代編集長であった長野規氏の清濁併せ持つキャラクター性が1番印象に残っている。2019/07/22
春雨
2
少年ジャンプの創刊から制作に携わっていた編集者の手記。主観も多く、含まれているので、鵜呑みにするのは確かに危険。けどそれ以上に価値がある。なぜアンケート重視主義なのか専属性というものできたのか、その一端を知ることのできる貴重な一冊。純粋に読んでて面白かった。一つ、注文をつけるとしたら、時系列が少し複雑になっていたとこ。2011/12/07
ぴょこたん
1
椎名誠の『新橋烏森口 純情編』のような実録青春記モノが好きな私にとって前半は楽しめた。またジャンプに連載された作品、特にリアルタイムで読んだ作品へのコメントなどは、裏話もあって興味深く読めた。ちばあきおなど、私の好きな漫画家が評価されている記述は自分のことのように嬉しかった。 ただ後半の大企業の派閥争いや権力闘争の話は読んでてあまり気持ちのいいものではない。もちろんそれだけ真に迫った内容なのだとの理解もできるが単なる個人の恨み節ともとれる。この点を筆者自身も認識した上で、「自分史」と銘打ったのだろう。2004/09/21
はたお
0
自分がジャンプを読み始めるより少し前の時代が中心。ジャンプの歴史と発展ぶりがよく分かる。最近の人だとそんなすごい時代があったことが信じられないだろうな。話が進むに従って自分の知っている漫画の話が出てくるので楽しく読めた。2017/07/31