目次
総論 “変態”を繙く―江戸川乱歩と梅原北明の“グロテスク”な抵抗
第1部 “変態”と向かい合う―精神医学・心理学(呉秀三―とらえどころのない“精神”と“正統派”精神病学;『変態心理』の頃の森田正馬;小熊虎之助と変態心理学)
第2部 膨張する“変態”―変態心理・変態性欲・霊術(変態する人・中村古峡―結節点としての『殻』;文学が“変態性欲”に出会うとき―谷崎潤一郎という“症例”;田中守平と渡辺藤交―霊術家は“変態”か)
第3部 “変態”の水脈―テクスト・表象(性的指向と戦争―大日本帝国陸軍大尉・綿貫六助の立ち位置;妄想される“女ごころ”―木々高太郎『折蘆』考;三島由紀夫―とてつもない“変態”;戦後空間を生きのびる“変態”―阿部定と熊沢天皇)
著者等紹介
竹内瑞穂[タケウチミズホ]
現在、愛知淑徳大学文学部准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
HANA
55
いや、面白い。変態は現在だと異常性欲者として使われることが多いが、過去にはもっと豊饒な意味を持つ言葉だった。本書は明治から大正、昭和初期とその世界に何らかの形を持つ人物を取り上げ変態とどう絡んだかを論じた一冊。取り上げられている内容も心理学に文学にジャーナリズム、人物も乱歩を始め潤一郎、三島に呉秀三、森田正馬と幅広い。変態を追う事で当時の精神医学の流れを追う事が出来るのは読み応えがあったが、個人的に興味があったのはやはり文学。潤一郎作品を通して変態の意味が社会に受容され変わっていく様等は出色の出来でした。2024/10/19
∃.狂茶党
8
タイトルに使っといて、乱歩への影響、乱歩からの影響はあまりないが、この話題について、大真面目に取り上げることは喜ばしい。 秋田昌美など、真面目な書き手はいろいろいましたが、ともすれば下品に傾きすぎる倒錯や変態といった、逸脱(とされるものの)文化史。 変態を指差す「規範」を形作る権力についての話題も読みたかったけれど、元々、読書会だったことを考えるなら、それは高望みだろう。 すこぶる面白いけど、これは、踏み台。 2022/06/21
gelatin
5
★★★★(★ とても面白かった…。ひっそりと後をつけるように、とある読友さんのレビューからこちらをセレクト。絶対に自分では知り得ない本をレビューされるので、本の海でこっち方面に進みたいときは羅針盤として最高なのである。えーと、こっち方面というのは、精神史とかサブカルチャー的なものね。谷崎は中公文庫から「谷崎マンガ」(中央公論社から出た「谷崎万華鏡」の文庫化)が出ており、変態としては定評があると思うのですが、この本を読んであらためてその偉業(?)に胸を打たれました。意図的、意識的に変態であるということ。2024/12/09
原玉幸子
0
「変態」を切り口にした、谷崎や三島の文学性が何たるやの論説を期待したのですが、歴史背景として、日本の精神病理医学や霊術に関わる記述が延々と続いたので、まぁいいや、と読み流してしまいました。(●2017年・秋)2020/02/20
-
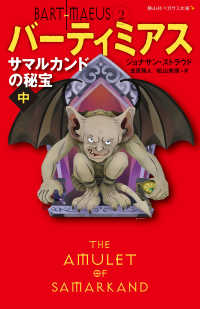
- 電子書籍
- バーティミアス サマルカンドの秘宝 中…







