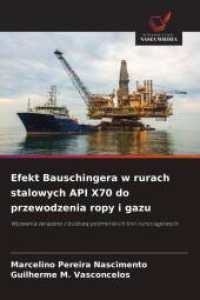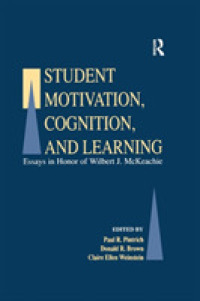内容説明
過去問題やオリジナル問題を使い、時間内に論文を設計し、合格レベルに仕上げるにはどうすればいいのか。一つ一つ確認しながら進めていきます。午後1問題の事例を使って、論文を設計する方法も説明しています。巻末ワークシートを使いながら、実践形式で、論文に対する恐怖感を払拭していきます。第2部には専門家による論文が36本も掲載されています。
目次
第1部 合格論文の書き方(本書を手にしたら読んでみる;論述式試験を突破する;基礎編;論文を作成する際の約束ごとを確認する;論文を設計して書く演習をする ほか)
第2部 論文事例(要件定義;開発(機能の設計)
開発(ソフトウェアの設計)
システムテスト・システム移行
組込みシステム)
著者等紹介
岡山昌二[オカヤマショウジ]
外資系製造業の情報システム部門に勤務の後、1999年から主に小論文がある情報処理試験対策の講師、試験対策書籍の執筆を本格的に開始する。システムアーキテクト、ITサービスマネージャ、プロジェクトマネージャ、ITストラテジスト、システム監査技術者試験の対策の講義とともに、コンサルティングを行いながら、(株)アイテックが出版しているシステムアーキテクト試験の「専門知識+午後問題」の重点対策、本試験問題集、予想問題集を執筆
樺沢祐二[カバサワユウジ]
防衛関係、官公庁系SIシステム、組込み系システムのソフトウェア開発業務に従事し、その後、プライバシーマーク審査の仕事に従事した。システムアナリスト、プロジェクトマネージャ、システム監査技術者、上級システムアドミニストレータ、情報セキュリティアドミニストレータ、テクニカルエンジニア(ネットワーク)、同(エンベデッドシステム)、同(システム管理)等を保有する。プライバシーマーク審査時は、ISMS審査員補及びプライバシーマーク審査員資格等を保有していた
鈴木久[スズキヒサシ]
1963年静岡県生まれ。専門分野は応用統計学、オペレーションズリサーチ、コンピュータ科学(工学部出身)。国内大手・外資系電機メーカに勤務、生産管理、品質管理、マーケティング、商品開発、情報システムの業務に携わり、利用部門の立場で業務とシステム化のかかわりに従事。独立後、システムの企画段階のコンサルティングや分析業務を手掛けるかたわら、情報処理技術者試験の論文対策指導を長年行っている
長嶋仁[ナガシマヒトシ]
業務アプリケーションの開発・カスタマサポート領域のSE業務を経て、研修講師と学習コンテンツ制作を中心に活動中。情報処理技術者(特種、システムアナリスト、上級システムアドミニストレータ、システム監査、テクニカルエンジニア(システム管理、ネットワーク、情報セキュリティ、データベース)など)、情報処理安全確保支援士、技術士(情報工学)
北條武[ホウジョウタケシ]
大手SIerに勤務しつつ情報処理技術者試験の教育に携わっている。主に公共分野のシステム開発に十数年従事した後、PMOでプロジェクトのリスクマネジメント等に携わり、現在は監査部で情報セキュリティ関連、SOX法対応の監査を行っている。保有資格はシステム監査技術者、システムアナリスト、プロジェクトマネージャ、テクニカルエンジニア(データベース)、情報セキュリティアドミニストレータ、PMP、公認内部監査人(CIA)等であり、また、2009年から一般社団法人プロジェクトマネジメント学会の委員も務めている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。