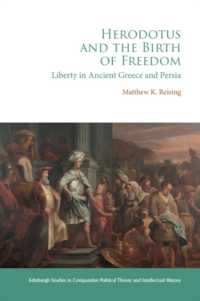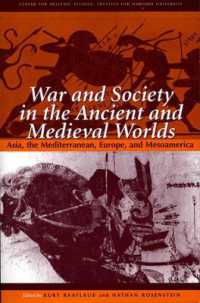内容説明
その国には二つの歴史がある。文化大革命、改革開放、習近平政権…語りとともに振り返る、建国期から二〇一九年まで。
目次
第1章 中華人民共和国の成立と初期建設の日々(建国期農村社会の大いなる変化;近代都市の形成と都市像 ほか)
第2章 社会主義体制への移行期(農村における公有化の受入れ;計画経済体制下における都市の生活 ほか)
第3章 人民公社と文化大革命の時代(調整政策のはじまり;社会主義教育運動と四清運動 ほか)
第4章 改革開放時代(一九七〇年代中国の国際関係と国内情勢;「包産到戸」の導入 ほか)
第5章 「反哺」の二一世紀(江沢民政権期;胡錦涛政権と「三農問題」 ほか)
著者等紹介
浜口允子[ハマグチノブコ]
放送大学名誉教授。専攻は東洋史学、中国近現代史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
さとうしん
13
包産到戸(農家生産請負制)が大躍進の頃から地方で個別的・実験的に導入され、改革開放期にも中央からの大動員ではなく、地方で自発的に導入され、そうした実践を通じて中央が認識を改めたというのは、「中国は一党独裁だから経済成長できた」という俗論の強い反証になるかもしれない。また反右派闘争は、毛沢東が民主党派に率直な意見・批判を求め、彼らが十二分にそれに応えてしまったところから始まったというのは、逆に建国当初は民主党派の役割が定まらない部分があったことを示していよう。2020/01/21
かんがく
10
「都市と農村」を軸に、中国の歴史を読み解く。具体的な数値・グラフなど客観的データが豊富な一方で、実際の中国の農村や都市で過ごした人物の逸話も挿入されていて、社会主義体制から現代中国への変動の実態がよくわかった。今後、戸籍改革がどこまで進むのか注目。2020/09/05
Hatann
6
中華人民共和国建国以降の都市と農村の二元的社会を概説し、農村問題に対する一連の政策を素描する。古代では農民が軍事費を支え、現代では農民が都市と工業化を支えた。支援体制を安定させるため、農民は移動の自由を制約され、社会保障・就業機会の格差を強いられた。改革開放路線後に農村を巡る環境は改善されるも、都市との格差は更に広がる。2000年以降は常に三農問題が最優先課題として取り上げられるが、格差が埋まる実感に繋がっていない。農村における農業以外の収入の仕組の重要性なども歴史的に説明される。簡易に纏まった良著。2020/03/04
さな
0
現代中国の入門として手に取った。文章に力があり、非常におもしろい。世界史は中途半端にしかやらなかったので、文化大革命や改革開放がどういうものなのか初めて理解した。以下、印象に残ったワードを挙げると、戸籍は戦後になって作られ農村と都市でわかれていること、農村人口が8割を占めていたこと、一号文件、人民公社と管理体制、生産体調のしんどさ、都市から農村への反哺の時代、意外にも中央政権が一農民の手紙を取り上げて対応していること、農村には社会保障がないことなど。2024/03/25
-
- 洋書
- Karma Vol.2