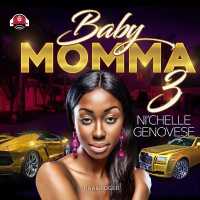内容説明
「通訳」という作業は、いったいどのような原理に基づいて行われるのか、通訳者の本質的な仕事とはなにか…。半世紀以上にわたって通訳という仕事の第一線に立ち続けてきた著者の、集大成とも言える「通訳論」「英語論」誕生!
目次
第1部 通訳とはなにか―日英通訳者の世界から(通訳とはなにか;通訳の現場/通訳者の仕事)
第2部 異文化コミュニケーションの目指すもの(文化とは?;パラグラフの構造が違う;通訳者はいかに文化の壁を乗り越えるか―日英通訳のひとつの例;異文化間コミュニケーションの意義;アメリカ手話通訳事情視察旅行)
第3部 日本のスピーカーへのお願い(通訳者に期待すべきでないこと;発言者のためのガイドライン)
著者等紹介
近藤正臣[コンドウマサオミ]
1942年愛知県生まれ。国際基督教大学教養学部社会科学科卒(在学中にアメリカ合衆国国務省付き随行通訳者として勤務)、同行政大学院修士課程修了。中央公論社、サイマル・インターナショナル、日本コンベンションサービス勤務を経て1976年より大東文化大学経済学部で35年間、教鞭をとる。2011年に日本通訳学会を設立、初代会長を務める。2013~14年、カリフォルニア州のモンテレー国際大学院にて、通訳を教える。現在、東京国際大学客員教授。大東文化大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
壱萬参仟縁
29
明治以来、日本の知識人は英語の構造・語法を日本語に押し付け、その過程で日本語をズタズタにしている(57頁)。通訳者も自分の価値、それまでの教育、育ちを持って、総動員して発言を聴き取れ、解釈できる(70頁)。著者は開発経済学の専門家でもある。開発と文化の通訳問題とも言える。情報は暗記するものだが、知識は理解するものだ(113頁)。通訳の職業病は胃潰瘍。胃痙攣の体験を著者は赤裸々に語る(119頁)。インドネシアでの20年前の体験とダブった。2016/02/22
ドシル
3
著者の長年の経験の集大成。 音声通訳も手話通訳も本当に同じなんだなぁと改めて感じた。 通訳スキルも同行通訳との関係なども共通点が、多々あり興味深い。 そして、使用言語を問わず社会からは通訳者という仕事は簡単に思われているんだなあ。。。2015/09/09
-

- 和書
- フランス語への旅立ち