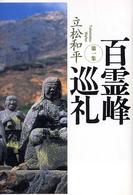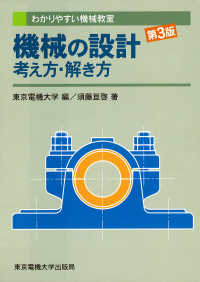内容説明
日本の死活問題=エネルギー資源の確保に隣国ロシアがもつ可能性とは。エネルギーをめぐる日ロのプロジェクトの現状を追い、さらに資源を仲立ちとする国際関係の安定化を構想する。
目次
第1章 日本による戦前のサハリン開発(サハリンの基本的な地質形成;サハリンでの石油開発と日本の参加)
第2章 戦後の日ソ経済協力―チュメニ油田開発構想とサハリン開発協力(日ソ経済委員会とチュメニ油田開発;田中内閣の資源外交;SODECOによるサハリン大陸棚開発協力;ヤクート天然ガス開発)
第3章 PS契約のもとでのサハリン大陸棚開発(サハリン1の動向;サハリン2の動向;サハリン3~5の石油・ガス開発事業)
第4章 ESPOパイプライン建設と日本の役割(極東にあらわれた新たな石油の流れ;東シベリア・太平洋パイプラインに見るロシアの戦略;なぜロシア原油が歓迎されているのか?;日本の中東依存度は低下した)
第5章 JOGMECが参入した東シベリア開発(東シベリアの特質;日露両国政府の合意;東シベリアでの日露共同事業;ロシアからエネルギー供給の持つ意味合い)
著者等紹介
本村眞澄[モトムラマスミ]
1950年生まれ。東京大学大学院理学系研究科地質学専門課程修士卒業後、石油公団に地質学専門家として入団。地質調査部、技術部、中国室、計画第一部ロシア・中央アジア室長、などを経て、現在その後継組織である(独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)調査部担当審議役。工学博士。オマーン、米国、アゼルバイジャンなどでの石油プロジェクトに携わった。オックスフォード・エネルギー研究所客員研究員(2001~02年)、北海道大学スラブ研究センター客員教授(2006~07年)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
DIVERmope
kenitirokikuti