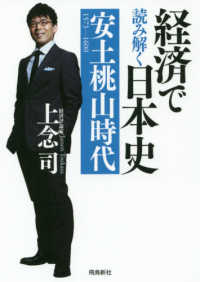内容説明
お金の流れがわかれば歴史がわかる。経済が発展すれば政治制度も変化せざるを得ない。貨幣量の変化を中世までさかのぼり、当時の景気循環を説明。室町幕府の衰退とともに、内乱と宗教戦争が頻発し、戦国時代に突入した原因はデフレ経済にあった。
目次
序に代えて―お金の流れがわかれば「歴史」がわかる
第1部 中世の「金融政策」と「景気」(明の景気が日本経済を左右した時代;室町幕府の知られざる財政事情)
第2部 謎解き寺社勢力(日本経済を牛耳る巨大マフィア;京都五山のビジネスと本願寺の苦難)
第3部 武将と僧侶の仁義なき戦い(信長の先駆者たち;吹き荒れる宗教戦争の嵐;信長の台頭と室町幕府の終焉)
あとがき 歴史教科書が教えない「経済的インセンティブ」
著者等紹介
上念司[ジョウネンツカサ]
1969年、東京都生まれ。中央大学法学部法律学科卒業。在学中は創立1901年の弁論部・辞達学会に所属。日本長期信用銀行、臨海セミナーを経て独立。2007年、経済評論家・勝間和代と株式会社「監査と分析」を設立。取締役・共同事業パートナーに就任(現在は代表取締役)。2010年、米国イェール大学経済学部の浜田宏一教授に師事し、薫陶を受ける。金融、財政、外交、防衛問題に精通し、積極的な評論、著述活動を展開している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
-





akky本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
saga
47
呉座勇一著『応仁の乱』と同時進行で本書を読む。歴史を経済学の視点から見ることの有益性を実感。国家を安堵する目的で輸入された仏教。しかし、先進国である中国・朝鮮へ仏教を学ぶと同時に、先進技術・物品の交易に関わり、宗教団体が経済マフィアにも喩えられるほど力を持っていったことも納得。比叡山延暦寺に僧兵がいることも、違和感なく受け入れられた。少し行き過ぎた著者の推論があるものの、学校の歴史教科書には欠落している考え方が面白い。2019/07/19
ころこ
35
歴史を分析して現在の経済を知ることも出来ますし、当時の経済を分析して、新たな史観の構築にもなります。独自通貨の発行が無かった当時は、4代・義持による日明貿易中断による銅銭の流入減少を、現在の金融引き締めと同じ効果があったと分析しています。6代・義教になって、日明貿易再開で金融政策の変更を行いますが、明側の制限によって十分に金融緩和はなされず、デフレ脱却は叶いませんでした。現在のデフレ脱却のヒントを探すという問題意識があると同時に、我々が抱く室町時代のイメージの暗さは、この経済状況に由来しているといいます。2020/01/19
Syo
28
読み応えあります。2022/01/19
ゆきこ
26
不景気になり人々の生活が悪くなると社会が乱れ、過激な思考が蔓延して争乱が始まる。そんないつの時代も変わらない「人間の性質」と「経済の掟」という視点から歴史を考察する一冊。上念さんのいつもの語り口で書かれていて、スラスラと読めるところが良かったです。室町時代の庶民の経済活動についてもっと詳しく知りたくなりました。2020/04/23
Kaz
22
経済で日本史を見ていくという視点が、新鮮でした。貨幣の価値については、無知極まりなかったので、正直半分も理解できていないのが恥ずかしいところなのですが・・・。知らなかったこと、理解できていなかったことがあまりにも多いことに赤面します。2019/08/25