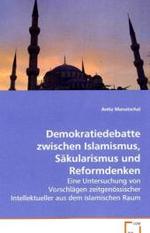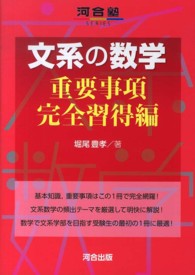- ホーム
- > 和書
- > 教養
- > ノンフィクション
- > ノンフィクションその他
内容説明
未曾有の災害と「幽霊」体験。亡き人を身近に感じ、ともに生きる“スピリチュアルな復興”の記録。昔話や民間伝承と重ねて、「死者の声」に寄り添う試み。
目次
第1幕 迫りくる危機と虫の知らせ(荒ぶる神々と予知能力;「虫の知らせ」とは;生死を分けた不思議なできごと)
第2幕 「助けて」という願望(海の中の出来事;「私に気づいて」という訴え;「この子だけでも」という切なる願い)
第3幕 あの日に帰りたい(帰るべき場所;止まった時間;生きている人を引き込む霊)
第4幕 見守っています(死者を祀る;復興が気になる霊たち)
著者等紹介
宇田川敬介[ウダガワケイスケ]
フリージャーナリスト、作家。1969年東京都生まれ。1994年中央大学法学部卒業、マイカルに入社。法務部にて企業交渉を担当。合併会社ワーナー・マイカルの運営、1995年に経営破綻した京都厚生会の買収、1998年に初の海外店舗「マイカル大連」出店、1999年に開業したショッピングセンター小樽ベイシティ(現ウイングベイ小樽)の開発などに携わる。マイカル破綻後に国会新聞社に入社、編集次長を務めた(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
yoshida
147
東日本大震災の前後に起きた様々な実話に、著者が考察を加えた作品。副題で「三陸の怪談」とあるが、怪談という表現は適切でないかなと思う。現在まで脈々と受け継がれて来た人々の営み。そこで得た災害の教訓が口伝や言伝えで残り、この震災でも救われた命があった。震災から時が経ち、生き延びた人々は亡くなった人々を悼む。その気持ちや想いが、科学では説明しきれない体験となるのではないか。亡くなった人々は、生き延びた人々の幸せを祈る。生き延びた人々は、亡くなった人々を悼む。繋がれた命が幸せを掴むこと。それが最大の供養だと思う。2019/06/03
AICHAN
59
図書館本。3.11の震災を予知した人の話、不思議な声や手に導かれて助かった人の話などを、東北に伝わる民話などとともに紹介している。不思議な話ばかりだった。この世の中には、科学では解明できない超常現象のようなものがあるのだと思った。2019/07/18
p.ntsk
56
東日本大震災前後に不思議な体験をされた方を取材しその話を収録したもの。単なる実話怪談としては読めなかったです。体験談の数々には怖さよりも哀切なメッセージを感じまた魂の実在も生々しく感じられました。震災直後の被災地はこの世とあの世の境界が曖昧になっていたのではと感じます。体験談の前後に挟まれる神話、民話、古典などから引用した著者の解説を読むにつけ自然や神々に対して畏敬の念を忘れた不調和な生き方を反省し、昔ながらの風習や伝統に込められた意味を今一度考え素直に受け入れ暮らすことの大事さに思い至りました。 2018/10/06
キンモクセイ
50
実話怪談が綴られていると思っていたら、ちょっと違った。昔から受け継がれてきた言い伝えや説明、考察が多い。その中でいくつか体験された方のエピソードが載っている。民話や昔話といった話には多くの知恵が隠されている。あのとてつもない出来事を経験した方はまた後世に体験を話し受け継がれていくのだろう。2020/04/17
澤水月
39
いわゆる実話怪談本と勝手違う、ある程度民俗学や民話知ってると本題に行くのに遠回り過ぎの嫌い…題材にためらいある為か。それぞれの章の頭に15pくらい海幸彦など神話、シカトの語源、飴買い幽霊とか説明は…体感不思議話の「本題」は全部の五分の一…でも子供をよろしくの話はすごくて飛び上がる。題材はいいので好みの問題、実本見てからが吉。2016/03/29
-

- 和書
- 形成的評価による授業改造