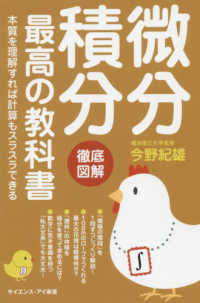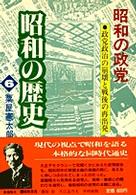- ホーム
- > 和書
- > 教育
- > 特別支援教育
- > 知的障害・発達障害等
内容説明
児童精神科医×作業療法士×理学療法士がタッグを組んだ最強のプログラム。子どもが伸びた!「NPO法人はびりす」での実践。「ついで」と運動プログラムを融合した、どんなズボラさんでも成功する家で保育園で簡単にできる習慣化メソッド!生活習慣改善プログラム32例。
目次
0 ついでをきっかけに子どもたちが変わる
1 発達障がいの多くは生活習慣病だと思っています
2 ついでにやろう!生活習慣プログラム集(気持ちのコントロール;ボディイメージ;しなやか姿勢;ねばりづよい足と指;なめらか動作)
3 生活習慣プログラム集 オマケの解説
4 3日坊主で終わらせない!どんなズボラさんでも成功できる習慣化メソッド
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かおりん
25
気持ちのコントロールに呼吸法が大事なのは分かる。生活習慣プログラム集で様々な動きや運動が紹介されているが、意識してついでにやれるかという問題がある。発達障害の子どもを多く見てきた私からすると、このプログラムを行うまでのプロセスは一律ではないし、全ての子が変わるとは思えない。プチコラムはなるほど~と楽しく読めた。2020/01/14
にこにこ
5
研修を受けたので、即復習。ロコモシンドロームが発達に影響あるとは・・・。健全な精神は健全な肉体に宿るのね。自分がまずロコモ状態なので小さな習慣をつけたいわ。子どもたちにはバランスクッションは試したので、斜面台をやってみたい所。危ないことやケンカのネタを排除したいと思うとどうしても遠ざけてしまうんだな。 人間はもともと口では呼吸できなかった!という。口呼吸をするしくみができていないのが誤嚥をしてしまう原因なのではなかろうかと思った。2022/02/12
鳩羽
4
体幹や足を鍛えること、呼吸法、など、日常的な生活や遊びの中に、うまくグッズなどを取り入れて、「ついで」にトレーニングをしていく方法を紹介する本。簡単なところでは、指が分かれている靴下をはくとか、斜面台の上で歯磨きをするとか、取り組みやすいものがたくさん紹介されている。今の子供が体をあまり使えていないことから、発達障害と診断されている子が増えたというスタンスなんだろうなという感じで、このトレーニングで少しでも改善するなら、それはそれでいいのかなという気もする。2024/06/02
-
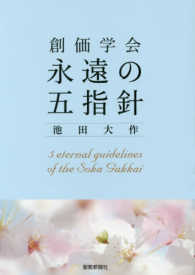
- 和書
- 創価学会永遠の五指針