内容説明
「できる・できないではなく、がんばっているわが子がステキと思える」発達支援事業所が増加する中、重要になる支援の仕組みづくり。障害を診断される前の時期から「育てにくさ」を感じたとき、相談し、安心して利用できる子育て支援の場があることの大切さと取り組みを、親、OT、PT、保育士、事業所、行政、さまざまな視点から紹介。「療育」とは何かを照らし出し、制度の整備、関係機関の連携を提起します。
目次
第1章 保護者からみた療育
第2章 職員からみた療育
第3章 3歳までのていねいな親子支援の取り組み
第4章 親子が安心して次の場に向かうことができるように支援する「移行支援」
第5章 自治体の仕組みづくり
第6章 “資料編”この間の国の施策動向と全通連の取り組み
著者等紹介
近藤直子[コンドウナオコ]
あいち障害者センター理事長、全国発達支援通園事業連絡協議会会長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
lovehunteru
1
保護者、職員からみた療育エピソードが為になった。保護者が療育に協力的でない場合はどうなってしまうんだろう。そういう事例も知りたい。2020/03/31
海戸 波斗
1
また、読んじゃった 2019/02/23
海戸 波斗
1
デベロップメンタルケアとともに読みたい。療育って家族総出で一家離散のもとになるって多いんだよな。まず、パパ側実家がギブからのパパもギブそして…無かった子どもになっていくのさ。産んだ母のみに自己責任だろってなりませんように。2018/12/10
たなか
0
事例から療育とはどうあるべきなのか考える。帯にある「できる・できないではなく、がんばっているわが子がステキと思える」が素敵、 早期発見のシステムは少しでも育てにくいという育児不安を支えるためで、上記の言葉のように保護者支援の一面がある。保護者支援により、保護者と子どもの愛着関係が良好になることのメリットは大きい。すべては子どもの発達保障に通じる。法改正など、発達支援の歴史をなぞることができ、そのために立ち上がってきた方々がいることを知り、改めて勉強したいと思った。2020/12/19
-

- 電子書籍
- ヴィジランテム(1) ビッグコミックス
-
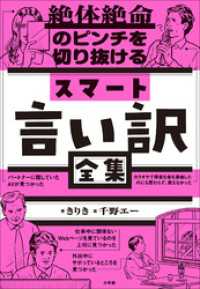
- 電子書籍
- 絶体絶命のピンチを切り抜ける スマート…







