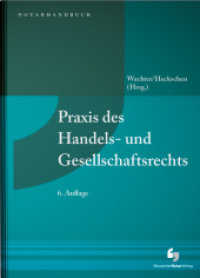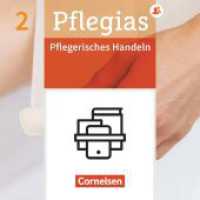内容説明
占領軍と引揚げ者がひしめいたモダン都市BEPPUの相貌―別府がBEPPUであった頃―日本戦後史の空白を、地域の戦後史に語らせる。そこから「個々の住民が体験した戦後」が初めて浮かび上がる。日本の地方都市にとって敗戦後とは何だったのか。
目次
第1章 戦後史へのアプローチ
第2章 モダニズム都市・別府
第3章 占領都市「BEPPU」
第4章 朝鮮戦争とBEPPU
第5章 戦災孤児・混血児の別府
第6章 「煉獄」の引揚げ者
第7章 阿南綾の戦後
第8章 「新生」の別府女性史
著者等紹介
下川正晴[シモカワマサハル]
1949年7月、鹿児島県国分市(現在の霧島市)生まれ。大阪大学法学部卒。立教大学大学院博士課程前期(比較文明論)修了。毎日新聞西部本社、東京本社外信部、ソウル支局、バンコク支局、編集委員、論説委員等を歴任。韓国外国語大学言論情報学部客員教授、大分県立芸術文化短期大学教授(マスメディア、現代韓国論)。「日韓次世代映画祭」(別府市)ディレクター。2015年定年退職し、近現代史、韓国、台湾、映画を中心に取材執筆中(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Tsuneyuki Hiroi
2
別府が引き揚げ船第1号の到着港であるとは知らなかった。そこでなりふり構わず力強く生き抜いた人々が描かれている。よく戦争中、空襲、原爆はよく描かれるが、戦後の苦しさはあまり語られない。だからこそ今、引き揚げの歴史は語られなければならないと感じるのである。2020/08/05
かっぱ
1
抜群におもしろかった。 戦前戦後を通じて、西瀬戸の拠点都市として発展し、「台湾、満州、朝鮮の各種勢力が入り交じるモダン都市であった別府」というのは、新鮮だった。私家本とオーラルヒストリーをふんだんに用いた物語は、ちょっとまねができないと思う。これが、このタイミングでまとめられているのはギリギリまにあった感がある。戦後の混乱期から朝鮮戦争にかけての社会の混乱の様子が忖度なくかかれていて、リアル。出典もきちんと書かれているので、気になれば自分で裏を取れるようになっているところも好感度高い。2025/02/14
しんい
1
大戦後の引揚げ者が多く住んだ別府の連合国占領下の歴史本のつもりで読んだが、引揚者よりも、大分県出身・縁の方々(著名人含む)の終戦直後期の人生や大分移住のエピソード集、という印象。著者は別府で短大の先生をなさっていた時期がある鹿児島出身の元毎日新聞記者の方。記者の方らしく、書籍調査とインタビューで調べた事実を中心に書かれており、また一人ひとりのエピソードはほぼ独立している。例えば、自決した阿南陸相の奥様の阿南綾氏が竹田居住時代に昭和天皇からお言葉をもらった件の発掘。著者の人選基準が理解できるとよかった。2020/08/30
ヨシモト@更新の度にナイスつけるの止めてね
1
戦前からの軍の保養地であり、際立ったモダニズム都市でもあった別府について、先人が細々と書いた幾つかの記録を除けば実に貧弱であった地域戦後史を、掘り起こしてまとめておきたい、という著者の労作。この本は発刊から徐々に話題になっているようだ。福岡の出版社、弦書房ならではの本だ。2020/06/28
-
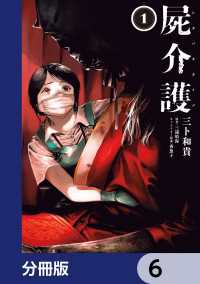
- 電子書籍
- 屍介護【分冊版】 6 青騎士コミックス