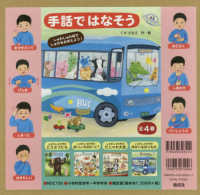内容説明
「えっ!知らなかった」ではすまされない、日本の水産業の大問題!!20年以上世界の水産業の現場を見てきた著者が提示する、日本の水産業復活の処方箋。
目次
第1章 待ったなし!の日本の水産業(国民が知らない日本の水産業の大問題;スペインやハワイの近海からサンマ? ほか)
第2章 なぜ日本は負け組になっているのか(消えたニシン;ニシンが消えた・ノルウェーの場合 ほか)
第3章 知られざる世界の水産業(天然物は横ばい;養殖物は成長の一途 ほか)
第4章 日本の水産業は必ず復活できる(科学的根拠に基づく資源管理の早期導入を;日本が取り入れるべき術は ほか)
著者等紹介
片野歩[カタノアユム]
1963年東京生まれ。早稲田大学商学部卒。マルハニチロ水産・水産第二部副部長。1995~2000年ロンドン駐在。90年より北欧を主体とした水産物の買付け業務の最前線に携わり現在に至る。特に世界第2位の輸出国として成長を続けているノルウェーには、20年以上毎年訪問を続けている。このほか中国の水産物加工にも携わる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Humbaba
4
資源は消費するだけではいずれ枯渇する。魚は時間を於けばたとえ何もしなくてもその数を増やしていく。しかし、ただ闇雲に乱獲するだけでは増える量よりも減る量が勝ってしまい、いずれ枯渇してしまう。個々の漁師は、自分たちの利益を最大化するために出来る限り漁獲高をあげようとする。それを抑えられるのは、国が厳密なルールを策定し、順守するしか方法がない。2014/01/03
こぺたろう
1
地方の一自治体でIQ導入を考える場合、近隣自治体と一緒に取り組むことが必要。そうしないと資源管理や流通戦略には効いてこない(その自治体で完結するなら話は別だけど、それは例外的)。水産上有用な魚種は、日本の広範囲に分布する種が多いことを考えると、やはりこれは国策でやらないといけないこと。片野さんの本は初見でないような気がしたが、2冊しか出されてないようなので、ひょっとしたら本書は既読かも。内容としては漁業者の自主管理に任せるのは限界がある。実効性のあるTACを設定すべきである、などが書かれている。2016/09/19
takao
0
乱獲が原因2016/08/13
のりすけ
0
海で釣りをする者からすると非常にショッキングなタイトルで、思わず手にとって一気読みしてしまった。近年は遊漁船レベルであっても高精度の魚探とソナーの両方を装備し魚の居所を的確に捉えるため、まずボウズ(釣果なし)で帰されることはない。この装備の発達を「魚もたいへんだなー」程度にしか思っていなかったが、その装備がアダとなって日本漁業がこまで疲弊しているとは正直絶句である。筆者が提案しているような漁獲枠を設定し、厳密に運用していくことが早期に求められる。2015/02/22
YusukeM
0
すごく興味深い内容。久米さんのラジオで聞いて興味を持って読んでみた。日本の漁業は大丈夫かな?と大変不安に思ってしまう。獲れば獲るほど自分たちの首を絞める、戦略なき乱獲。こんな原始的な漁業をしていたとはカルチャーショック。日本の魚ブランディング再興を願います。2015/01/26
-
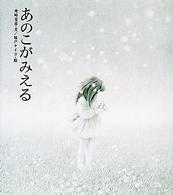
- 和書
- あのこがみえる