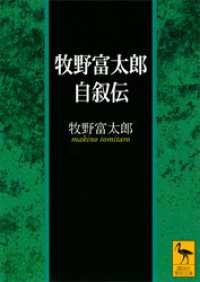目次
1 解釈学的神学の現在―二〇世紀半ば以降における解釈学的神学の展開
2 ニーチェとパウロ―『曙光』アフォリズム六八節におけるパウロ批判をめぐって
3 絶対無と神
4 ガラテヤ人への手紙三章一節の「十字架につけられた(イエス・キリスト)」の解釈
5 パウロにおける悪と罪―ローマ人への手紙七章一四節b‐二一節の釈義的解釈学的考察を中心に
6 パウロの「唯一神」理解―コリント人への第一の手紙八章四節―六節の釈義的解釈学的考察
7 The New Perspective on Paulの解釈学的検討
著者等紹介
松木真一[マツキシンイチ]
1944年熊本県に生まれる。1969年関西学院大学大学院神学研究科修士課程修了。京都大学文学部キリスト教学を経て、チューリッヒ大学に留学。現在、関西学院大学教授。神学博士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
うえ
6
「ニーチェはパウロを語るとき、キリスト教攻撃の主要人物として彼を相当の憎悪をもって弾劾する。それは、この『曙光』においてもすでに始まっている。それよりも、同書アフォリズム68節は他のアフォリズムと比べて、かなりの分量で集中的にパウロを論じ、内容的にも律法問題やキリストの十字架死、キリスト顕現、パウロの回心といったパウロ神学にとっても中心に触れるような問題を取り扱っている。…ニーチェ自身がこの『曙光』の時期をふりかえって、「この書によって、私の道徳への征戦が始まる」(『この人を見よ』)と回顧している」2022/01/02
いとう・しんご
3
読み進めながら「どこが解釈学なんだべぇ」と思っていたら、一番最後に「ブルトマン以来の伝統的解釈を批判的に継承展開してきた解釈学的神学」P155という言葉が出てきて、改めて、第1章を見返してみたら、哲学の分野で言う解釈学とは無関係と言うことが分かったのでした。でも、ブルトマン以来の神学者の教説や言葉がパッチワークになっていて、かつ、最新の色々な神学的な動向を知ることも出来たと言う意味では、勉強になりました。2022/01/12