出版社内容情報
正解だけを追求し、それ以外を認めないなんてもったいない!
教育現場だけでなく、企業や大学からも熱視線を集める
“肩書き迷子の山内さん”が、
子どもも大人も、創造力が“自然と呼び覚まされちゃう”
方法論とワークを初公開!
・「折り紙モデル」ではなく「砂場モデル」
・「なんとなくセンサー」を働かせる
・ものを介した「三角の関係」で対話を深める
【目次】
はじめに
Part 1 「つくる」ってなに?
――折り紙モデルと砂場モデルで2つの「つくる」を見比べる
1.「つくる」を考えてみる
2.「学ぶ」を考えてみる
3.「つくる」をさらに考えてみる
4.成功か失敗か、それしかないの?
5.〈ワーク1〉よーく見て、描いて、語る
Part 2 「つくる」は考える?
――勝手で素敵な思い付きは「手」から始まる
6.「へぇ!」から「あ!」へ
7.思いつきは「手」からはじまる
8.手で考える子どもたちと共創する場のデザイン
9.〈ワーク2〉紙からさがす・語る
Part 3 「つくる」はコミュニケーション?
――三角の関係が生み出す新しい「ひらめき」
10.コミュニケーションを考える
11.哲学対話
12.〈ワーク3〉光らせて、カタチをみて、語る
Part 4 「つくる」をほぐす
――「造形対話」でプロセスから学びを生み出す
13.思いつきを躊躇なく放て
14.秀作と駄作
15.「造形対話」という提案
16.造形対話をやってみよう!
17.造形対話の実践例〈子ども編〉
18.造形対話の実践例〈大人編〉
Part 5 「つくる」をまとえる場をつくる
――10年続けた「くだらない場づくり」で見えてきたこと
19.安心して「つくる」ができる場を――図工室とVIVISTOP NITOBE
20.誰もが、軽やかな「つくる」をまとえるように
おわりに
内容説明
大人も子どもも、ともにつくり、ともに学ぶVIVISTOP NITOBEコミュニティクリエイティブディレクターが、「完成・正解の呪縛」を解き放つ、創造力が自然とあふれ出す方法論とワークを初公開!「折り紙モデル」ではなく「砂場モデル」。共創する場をデザインする4つのステップ。ものを介した「三角の関係」で対話を深める。「つくる」の価値は、全部「途中」にあった!
目次
1 「つくる」ってなに? 折り紙モデルと砂場モデルで2つの「つくる」を見比べる(「つくる」を考えてみる;「学ぶ」を考えてみる ほか)
2 「つくる」は考える? 勝手で素敵な思いつきは「手」から始まる(「へぇ~」から「あ!」へ;思いつきは「手」から始まる ほか)
3 「つくる」はコミュニケーション? 三角の関係が生み出す新しい「ひらめき」(コミュニケーションを考える;哲学対話 ほか)
4 「つくる」をほぐす 「造形対話」でプロセスから学びを生み出す(思いつをき躊躇なく放て;秀作と駄作 ほか)
5 「つくる」をまとえる場をつくる 10年続けた「くだらない場づくり」で見えてきたこと(安心して「つくる」ができる場を―図工室とVIVISTOP NITOBE;誰もが、かろやかな「つくる」をまとえるように)
著者等紹介
山内佑輔[ヤマウチユウスケ]
学習環境デザイナー。新渡戸文化学園VIVISTOP NITOBEコミュニティクリエイティブディレクター。東京造形大学特任准教授。大学職員、公立小学校の図工専科教員を経て、2020年4月に新渡戸文化学園へ着任。子どもたちがやりたいと思う気持ちのままにつくったり試したりできる、偶然性に開かれた空間「VIVISTOP」を運営するVIVITAと連携し、新渡戸文化学園内にVIVISTOP NITOBEを開設し、その運営を担当。2025年から東京造形大学特任准教授に就任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-
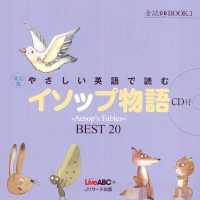
- 電子書籍
- 音読 BOOK (1)改訂版 やさしい…







