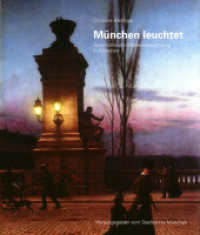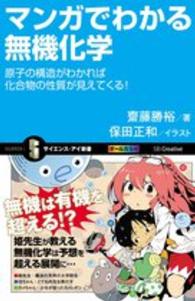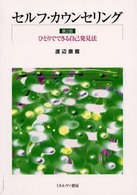内容説明
なぜトワイライトエクスプレスの人気スイートは、2室しかないのか?なぜJRは、Suica、ICOCAの普及に力を入れるのか?鉄道会社が仕掛けるあの人気サービスの「儲けのしくみ」がわかる。
目次
1 山手線と東海道新幹線では、どちらが儲かっているのか―営業損益における売上とコスト
2 トワイライトエクスプレスのスイートが2部屋しかない理由―利益を最大化させる仕組み
3 大阪環状線に40年前の車両が走っているワケ―ストックを活かした資本投下
4 東海道新幹線を最安値で利用する方法―固定費と売上の関係
5 なぜ回数券や割引切符の種類がやたら多いのか―競合対策と価格設定の関係
6 Suica、ICOCAの普及をJRが進める理由―販売システムの多角化と手数料収入
著者等紹介
中嶋茂夫[ナカジマシゲオ]
株式会社中嶋商店代表取締役。インターネット活用コンサルタント。1967年大阪生まれ。京都工芸繊維大学繊維学部高分子学科、ニューヨークFashion Institute of Technology卒業。ネットを活用した売上アップやコスト削減の講演会、顧問契約先の訪問で全国各地を飛び回る(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mitei
209
タイトルの件だけかと思いきや関西とかいろんな電車の利益をどうとっているのかが勉強のなった。トワイライトエクスプレスはもう無くなったんだったなぁ。残念。2020/06/07
手押し戦車
13
設備投資を少なくして回転率を上げると維持修繕費や営業費が高いが原価償却費が下がりコストを軽く薄利多売型になり、長距離型は設備投資が高くなり総資産回転率は低くなる分、圧倒的なインフラ設備により競争力あり参入障壁が高く市場が寡占になり価格決定権が強く利用者が使わざるを得なくなる。さらに相乗効果で観光地に投資をして通行料を割安にして旅行パックにして集客数を最大にしてグループ連結で収益を出す。割引きをしても連結収益が増える。回転率から見ると短距離、収益力から見ると長距離が強い。2015/01/27
-

- 洋書
- SORRY MOM