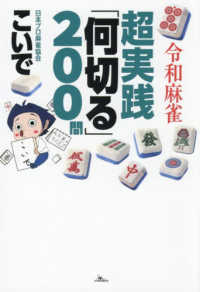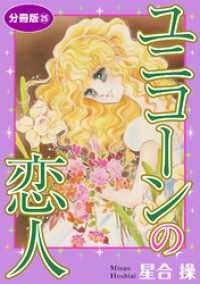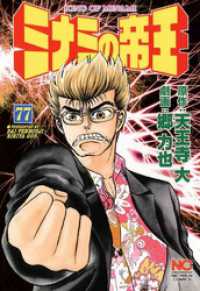内容説明
大東亜共栄の夢を愚直に信じ、中野学校出身者、ハリマオなど少数の精鋭を率いてマレイ、スマトラの民族解放工作に奔走、その一方でインド国民軍を創設しインド独立運動の巨頭チャンドラ・ボースを迎えるという驚くべき成果をあげた藤原少佐とF(藤原)機関。その栄光と挫折の軌跡を機関長藤原少佐が自ら詳細に綴った貴重な手記。
目次
第1部 藤原機関(志士の暗躍;バンコック潜行;密会;飛電;覆面を脱いだIIL;アロルスターへ;決起;スリム戦線;首都クアラルンプール;シンガポール;東京会談;惜別)
第2部 その後(モハンシン事件;インパール進撃;デリー軍事法廷;訊問;附記)
著者等紹介
藤原岩市[フジワライワイチ]
1908年兵庫県に生まれる。1931年陸軍士官学校卒。1938年陸軍大学校卒。歩兵第37連隊中隊長、第21軍参謀を歴任。1939年大本営参謀本部に転任。第8課で広報・宣伝を担当する。1941年タイ・バンコックに赴任、南方軍参謀兼任の特務機関(F機関)機関長として活動を開始する。主な任務はマレイ、スマトラ、インドの独立運動の支援と対日融和政策の推進。英印軍将校モハンシンらとともにINA(インド国民軍)の創設、インド独立運動のリーダー、チャンドラ・ボースの招聘など、多大な成果をあげる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Willie the Wildcat
36
言語、地理、そして人脈も限られた中での思想戦。「アジア解放」の大義の下、根底の情熱と信念、そして謙虚さが心の拠り所。マレイ人、インド人・・・と、”夢”に向かう過程の変化が見所。特にIIL、INAなど、同じ民族での内部闘争の収束と新たな団結が印象的。デリー軍事法廷でのデサイ弁護士に、パール判事を重ねる。一方、掲げる大義と中国人差別といった現実との矛盾。大本営、現場将校の一貫性の欠ける戦術と言動が、F機関には致命的。神出鬼没ハリマオの宿命も、哀しき時代を反映。巻末のモハンシン将軍の口述が、数少ない救い。2015/07/12
けじ
1
以前から「F機関」という名前はあちらこちらで聞いていたが、実態が不明で興味があったので読んでみた。本人の手記ということもあり、幾分割り引いて考えないといけない部分はあるが、それでも先達の偉大さが胸に響いてくる。戦前の昭和史は未だに暗いイメージが色濃く残っているが、全てがそうではないということを教えてくれる良書。2013/04/09
勝浩1958
1
結果的にインド独立にF機関のメイジャー・フジワラの果たした役割は大きかったようである。でも、日本の軍部はどこまで真剣にインドの独立を考えていたのであろうか。大東亜共栄圏というイデオロギーは、日本人の独善であって、どれ程東南アジアの人々に理解されていたのであろうか。この手記を読むかぎりでは、イデオロギーへの信奉より、藤原氏個人への尊崇の気持ちの方が優っていることは間違いない。 それにしても、なんと誤植の多い書籍であったことか。あまりにも酷過ぎた。2012/08/22
リョウスケ2k3
0
★★★★☆第二次世界大戦に実在した日本の『F機関』という存在を知っている日本人がどれだけいるだろうか?当方も本書を勧められるまで知らなかったです。『大東亜共栄圏』は本当の意味は欧米列強の植民地から独立解放してアジア人のアジア人のための国を作ることだった。インドがイギリスから独立をするに至った経緯に日本がどれほど関わっていたのか。本書はその当事者であった藤原岩市が書いた手記に基づく貴重さ良書。だたし時代の関係上やや読みづらい・・・。やむなしか。2016/11/04
kikizo
0
実話だが、少し読みにくい。難しい言葉を平気で使うのに、簡単な漢字を仮名でそれもルビ付きで書いている。あまり知られていない歴史書として読むべき書である。興味本位だとちょっとしんどいかな?2012/12/09