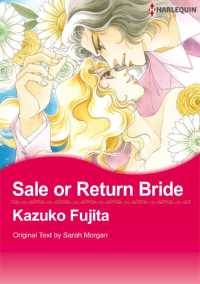出版社内容情報
天皇制の起源に遡り、神道・道教・修験・天台・真言・後醍醐など、天皇を軸として習合・展開されてきた日本的霊性の原型を根源的に探求。
内容説明
天皇制の起源に遡り、神道・道教・修験・天台・真言・後醍醐など、天皇を軸として習合・展開されてきた日本的霊性の原型を根源的に探求。
目次
翁の変容
翁の発生
国栖
小角
修験
空海
天台
一遍
後醍醐
後記 後醍醐から現在へ
著者等紹介
安藤礼二[アンドウレイジ]
1967年、東京生まれ。文芸評論家。多摩美術大学教授。同芸術人類学研究所所員。早稲田大学第一文学部考古学専修を卒業。出版社編集者を経て、2002年「神々の闘争―折口信夫論」で群像新人文学賞評論部門優秀作を受賞。元出版社勤務(雑誌・書籍編集)。元早稲田大学大学院非常勤講師。2006年『神々の闘争 折口信夫論』(講談社)で芸術選奨文部科学大臣賞新人賞を受賞。2009年『光の曼陀羅 日本文学論』(同)で大江健三郎賞と伊藤整文学賞を受賞。2015年『折口信夫』(同)でサントリー学芸賞と角川財団学芸賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
hasegawa noboru
3
〈神道・道教・修験・天台・真言・後醍醐など、天皇を軸として習合・展開されてきた日本的霊性の原型を根源的に探究。〉(帯コピー)日本思想とその実践の底流にあるものを多角的スペクタクルに探り、あぶり出し整理した美しい考察の文章。筆者によれば「祝祭学は芸術と歴史学、宗教学と哲学の交点に形づくられる」可能性としての未来の学であるという。近代のいびつを超えるためには、政治、現実の革命だけはなく、宗教、解釈の革命(歴史の見直しということか)が必要だと説く(後記)壮大な意図のもとになされた文芸評論。学術論文ではない。2020/01/31
takao
1
ふむ2020/01/18
ishii.mg
0
純粋な神道とか、純粋な仏教というものは存在しない。すべて習合しつづけて、時に純粋を求めて、変化し続けてきたのだ。一方北畠親房、宣長、篤胤たちは、天皇制の原型ではなく起原を求めて純化の傾向にあったのかもしれない。全体として最澄の天台の流れ、源信から一遍の念仏の流れなどコンパクトでわかりやすかった。2021/10/04
かんちゃん
0
なかなかハードな内容でした。日本の有り様を知るのは、とても興味深いものがあります。これからも、どんどん読み続けていきたいものです。2020/04/13
渓流
0
民俗は面白し。こう、飯の種にもならないことに現を抜かし、それを出版してくれる会社があるってことが成熟社会の証。AIで効率を求めるだけじゃ、温かな心など育まれないし、つまらん社会になっちゃう。銭儲けで禿がすすむ人を見るより余程いい。 2019/12/28