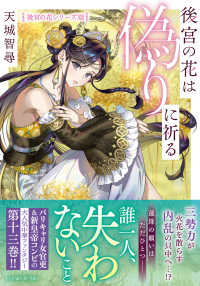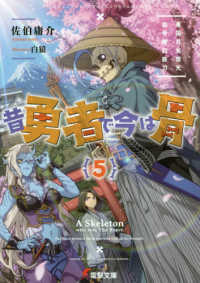内容説明
各地に残る「蘇民将来子孫」の伝説。「備後風土記」にも描かれ、千数百年にわたって民衆に支持されてきたこの神々とはいったいどういう神か。土着的でありながら記紀神話とは異質の蕃神性を伴う神格の由来を辿り、日本人の魂の源泉を探る渾身の書き下ろし。
目次
蘇民将来のお守り
第1部 備後から京都へ(「祗園」へ通う道;蘇民将来はどこから来たか;婆梨采女とは誰か;牛頭天王の変遷)
第2部 伊勢から津島へ(伊勢と蘇民の森;津島天王社とその祭)
第3部 近江から物部村へ(牛尾山曼荼羅;八王子神群像;物部村の陰陽師たち)
第4部 みちのくの蘇民たち(蘇民祭と妙見信仰;摩多羅神の夜;悪路王の末裔たち)
著者等紹介
川村湊[カワムラミナト]
1951年、北海道生まれ。1982~86年、韓国釜山の東亜大学で日本語・日本文学を教える。法政大学国際文化学部教授。文芸評論家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
榊原 香織
78
面白いな~。民俗学のいいとこどりだな 奥三河、花祭りの祭文から四国山奥のいざなぎ流、対馬からの伝播、はては宮沢賢治まで。ラブクラフトまで出てきたりして。 静岡の竜爪山も出てくる。雨乞い信仰。 蘇民将来関係で行ったとこも結構ある 上田の国分寺跡、千葉の七王塚、対馬、津島、伊勢などなど 前に読んだかもしれないけど、面白いからよいや2021/09/10
佐倉
13
祇園祭で祀られる神であり、各地の蘇民将来子孫也の札などで残滓が残る牛頭天王。記紀神話の外にある存在であるため廃仏毀釈以降は垂迹とされたスサノオに置き換えられたが、スサノオだけでは解釈しきれない疫病や来訪者観が反映された神と言える。備後国風土記には武塔神(後に牛頭天の父とされる)と表記されていたが、武塔は読みが朝鮮の宗教者・巫堂(ムーダン)と近く巫堂の始祖パリ公主とは頗梨采女とハリ=パリ+称号で共通点が見られるという。ソミンとコタンの名前も朝鮮語で解釈できるなど東アジア圏の信仰として捉える視点が興味深い。2024/12/11
paxomnibus
2
直前に読んだ「日本人の死生観」に一カ所だけ「牛頭天王」に関する記述があったが、その前に読んだ同様の本には全然なかった。本書によると明治の廃仏毀釈・神仏分離のせいで存在を消されたらしい。各地に残る神社にその名残を求めて旅する著者の紀行文が混じっているのがちょっととりとめない感じ。とはいえ神社の名前にそれぞれ由来があることさえ知らなかった私にはいい勉強になった。素戔嗚神社は近くにもあるが、そんないわれがあるとは全く知らなかった。かつての神々の物語が時代と共に変わっていくのも面白い。しかしよく調べたものだと感心2021/12/07
コウみん
2
アマビエと一緒に疫病の神として呼ばれている牛頭天王。 どこから来た神なのか日本人からどんな風に牛頭天王が受け入れたのか。 この本では牛頭天王を朝鮮半島のシャーマン文化と連関して説明してあり、日本での民間信仰を教えてくれている。2021/08/11
H masa
1
「牛頭神社」という名前を見かけて、何だろうと思ったのが読むきっかけ。神社ではスサノオノミコトにも比定されるが、元々はインドからの渡来神であるらしい。それも、疫病をもたらす悪鬼! 悪病をもたらすなら病を鎮める力もあるだろうと疫病除けのご利益を求めて信仰も広まっていったという。そこに仏教やら陰陽道やら道教やら神道やらがかぶさって複雑怪奇なことになっている。祇園社も牛頭信仰の神社だったし(天神さん必ずしも菅原道真ならず)2019/09/01