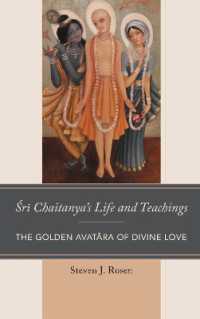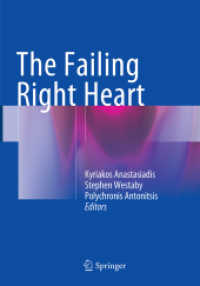内容説明
カナダの狩猟民カスカと共に暮らし、狩りをし、肉を解体し、食べる。そこから動物とのあるべき接し方やひとと動物の関係を考える民族誌。
目次
第1章 ヘラジカの贈り物
第2章 カナダ先住民カスカ
第3章 今日の狩猟採集活動
第4章 狩猟を学ぶ
第5章 カスカの民族動物
第6章 狩猟民カスカの今日
著者等紹介
山口未花子[ヤマグチミカコ]
1976年生。北九州市立大学特任講師。動物に対する深い関心から、人と動物との関係について明らかにするため、動物生態学や生体人類学、文化人類学の方法を学ぶ。2005年より、カナダ・ユーコン準州の先住民カスカの古老より動物に関するさまざまな実践を学んでいる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ワッピー
24
カナダ西方のカスカインディアンの中で、狩猟生活を通じて、動物と人間の交流を探るフィールドワーク。白人の持ち込んだいろいろなツールを生活に取り込みつつも自分たちの価値観・手法(デネ・ケ)を残しているという意味ではしたたかです。今でもこういった狩猟生活が成立しているエリアがあることには感動しますが、おそらく現代世界に次第に包囲され、狭まりつつある最後の島の1つかもしれないと考えると悲しくもあります。動物と人間との関連性については、デスコーラの「人間と非人間の連続性の4つのモード」はかなり参考になりました。2014/06/01
Akihiro Nishio
22
先月講演を聞いた先生の本。カナダのユーコン準州を中心に住む今も狩猟採取活動を生活の中心に据えている少数民族カスカと共に生活し、狩猟活動に参加しながら、彼らのの生活ぶり、狩猟の技術、信仰、動物との関わりなどを記録した大著であった。筆者の言うように人類の歴史の99%以上は狩猟採取生活をしていたのであるから、人類の生活の規範や考え方の多くは狩猟採取時代に培われたものに違いない。こうしたカスカのフィールドワークから現代人が学べるものは計り知れない。岐阜大学は良い先生を得ましたね!2017/01/15
キニマ
7
今日もなお狩猟が日常の一部として行われているカナダ西部の民族カスカ、彼らの世界では人間が根源的に動物との営みの中で育んできた価値観や我々の生き方を想起させるとともに今の私たちが失った様々な問題を気付かせる。カスカ民族は動物と個人のつながりを集団の最小単位と据えており狩場に長期滞在も茶飯事だ。そこで培ったのは人と動物の贈与関係、動物を人間という種とは独立した個性と役割をもつものと考え物語を通じて人間との連続性を維持しているということ。トーテミズムやシャーマニズムの考え方もつながりにはかかせない。2018/05/13
aof
5
カスカの人々が動物との間に築いてきた、世界にも類を見ないほどに豊かな自然誌。別の雑誌で作者の山口さんが、カスカの人々と動物が互酬的な贈与関係を結んでいると話していたのを読んで、ぜひこの人の研究を知りたいと思って読んだのだけど、やっぱり面白かった。 動物がパートナーである社会は、それはそれとして成立するんだよな〜と不思議な気持ちで読んだ。自然とともに生きるって、日本で聞くと画一的な感じがするけど、本当はもっと多様なんだろうな。2019/11/05
テッテレこだち
2
北アメリカのファーストネイションのひとつであるカスカについて、著者自身のフィールドワークから、狩猟や採取等の様子、動物との関わりかたを研究した本。白人の道具や生活スタイルも取り入れつつ、狩猟を中心としたブッシュの中での生活も組み込んだ伝統的なライフサイクルを生きる人々の、ある種の柔軟さが印象的だった。写真版も多くてわかりやすかった。2024/09/18