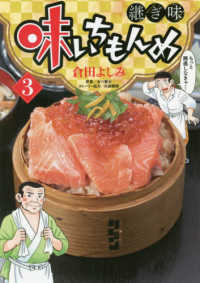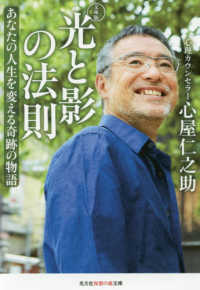出版社内容情報
吉備地域の製鉄遺跡を網羅した、吉備地域における製鉄技術史研究の到達点。鉄生産を担った先人たちは、より良質な鉄をより多く作るために技術の改良を繰り返してきた。製鉄遺跡を手がかりに、たたら製鉄の歴史に迫る!
第一章 たたらとは
一 たたらとは 10
二 たたら吹製鉄法 13
三 踏鞴 15
四 製鉄炉 16
五 床釣り施設 17
六 製鉄遺跡としてのたたら 20
第二章 製鉄起源の追究
第一節 各地域での初例発見まで(一九五〇年代~一九七〇年代前半)
一 岡山市横井の「カンナ流し跡」 23
二 初めての製鉄遺跡の発掘 福本たたら遺跡 24
三 試行錯誤のトレンチ調査 石生天皇遺跡 26
四 たたら研究会の発足 29
五 備後では筒形炉を発見 常定峯双製鉄遺跡 30
六 中国山地の麓を掘る 高本遺跡ほか 31
七 「ヤツメウナギ」は炭窯か否か 34
第二節 活況を呈する美作・備後での調査(一九七〇年代後半~一九八〇年代前半)
一 山芋掘り転じて発掘へ キナザコ製鉄遺跡 38
二 鉄穴流し跡を掘る 糘山遺跡群 41
三 ついに前方後円墳時代の製鉄遺跡を発見 大蔵池南製鉄遺跡 46
四 広島大学、中国地方の製鉄遺跡の体系的研究を開始 50
五 「ヤツメウナギ」を壊して造られた製鉄炉 緑山遺跡 52
第三節 備中南部は一大製鉄地域(一九29
(四) D区の製鉄炉 131
(五) 近世たたら床釣り施設の成立過程に迫る 133
六 最近の調査から 138
第四章 吉備におけるたたら研究の現状と課題
一 弥生時代に製鉄は行われたのか 140
二 鉄生産に関する新技術の導入 143
三 鉄鉱石と砂鉄 144
四 箱形炉と筒形炉 146
五 中世の製鉄 148
六 たたら吹製鉄法の成立 149
七 たたらの終焉 152
吉備地域製鉄関連遺跡分布図 160
中国山地に分け入り、人里を離れた谷間を歩いていると、足下に黒く鈍く光るものを見つけることがある。自然の石とは思えず、アスファルトのかけらのようにも見えるがもっと硬く、表面にぷつぷつと穴が空いていたりする。ところによって呼び名は違うが、「カナクロ」とか「カナクソ」と呼ばれるこの奇妙な物こそ、昔の人が鉄を採った後に残された滓、すなわち鉄滓である。
足下の鉄滓が、ごろごろとたくさんあったなら、少し観察してみよう。濃いこげ茶色をして、割れ口にところどころ穴が空いていて、溶岩が流れたような皺が見える。手に取ると、ずっしり重い。これは、炉から流し出された、鉄分の少ない鉄滓である。表面に橙色の粉を吹いたように錆が浮き、木炭のかけらがこびり付いたような跡が見えれば、最後に炉の中に残ったものだ。そして、割れ口が黒いガラスのように光って、その中に白い粒々が見え、片側に焼けた粘土が残っていたら、それはまさしく、鉄を採った炉の壁の一部である。
さて、足下の鉄滓から、これだけの状況証拠が揃ったら、直ぐ近くに「たたら」の跡があることは、もう間違いない。ここが、製鉄遺跡である。しかし、その「たたら」の跡を掘り出すのはとても難しい
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
rbyawa
-

- 和書
- 連続体の解析力学