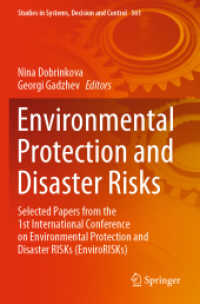出版社内容情報
序 章 岡山後楽園 (御後園) の築庭とその利用に関する研究
一、 研究の目的とその視点 23
二、 御後園の概略と研究課題 30
三、 文献史料 36
四、 絵図― 「御後園」 関係絵図― 50
五、 御後園の築庭と景観の変遷の概略 51
第一章 岡山藩主池田綱政の築庭とその利用
一、 築庭とその背景―大名の生活― 69
二、 御後園の利用状況 102
第二章 藩主池田継政以後の藩主と 「御後園」 利用の概略
一、 藩主池田継政の利用 185
二、 藩主池田宗政の利用 208
三、 藩主池田治政の利用 218
四、 藩主池田斉政の利用 237
五、 藩主池田斉敏の利用 258
六、 藩主池田慶政の利用 271
七、 藩主池田茂政の利用 285
八、 藩主池田章政の利用 291
第三章 藩主と御後園の利用
一、 藩主と武芸 303
二、 藩主と能 324
三、 藩主と茶の湯 338
四、 藩主と浄瑠璃 363
第四章 御後園と菜園
一、 御後園と菜園 383
二、 御後園における田植行事 384
三、 御後園内の茶畑と茶摘 400
四、 菜園の栽培作物 405
第五章 江戸時代の大名庭園と神仏信仰
一、 大名庭園と神仏信仰 425
二、 「慈眼の維持管理 599
三、 御後園の人員構成 608
四、 御後園へ渡る 「仮橋」 の維持管理 616
第九章 結び
一、 研究の視点―藩主の御後園利用― 625
二、 築庭の目的と利用の変化 627
三、 大名庭園 (岡山後楽園) 築庭の目的と意味について 635
四、 御後園の利用と保存に関する将来的課題 638
『参考資料』
別表 「藩主池田綱政の御後園における能の興行と拝見者一覧表 (宝永四年から正徳四年)」 641
あとがき 673
はじめに
日本庭園の研究は、 従来種々の視点から研究されてきた。 なかでも、 日本庭園の美を追求する研究では、 庭園が如何なる造形様式で造園されたか、 あるいは如何なる思想が造園の背景にあるか、 また、 造園に使用された石材や樹木の種類、 石材の産出場所など、 研究者の追究する問題点ごとに、 多くの研究成果があげられてきた。 ここに岡山後楽園 (江戸時代は 「御後園」 (ごこうえん) と呼称された) を取り上げた研究では、 築庭した岡山藩主が、 如何に庭園を利用したかという視点から研究調査を試みた。 岡山藩主池田綱政が、 造園して利用を開始した元禄二年 (一六八九) から、 江戸時代最後の岡山藩主池田章政が、 利用を終了する明治四年 (一八七一) までの約百八十年間にわたり、 各藩主たちが 「御後園」 を如何に利用したかを明らかにする調査検討を行った。
江戸時代に造られた大名庭園は、 最近では観光の対象となる史蹟として注目され、 庭園内では種々の行事が四季折々に行われている。 そして観光客を集める行事が実施される時、 江戸時代の大名生活を再現する行事も多く試みられている。 しかし、 世間一般に観光対象資源として注目されながら、 大名庭園の歴史研究は、 多くの場合、 歴史史料のな研究へと発展させる必要がる。 岡山後楽園の場合、 庭園を造り利用した藩主たちの生活の歴史を記した史料である 『日次記』 (藩主の日々の生活の要点を記載した日録)、 岡山後楽園の日々の様子を記録した 『御後園諸事留帳』、 それに多くの絵図などが、 「池田家文庫」 (岡山大学附属図書館) に所蔵されているので、 これらの史料を詳細に研究することにより、 江戸時代の 「大名庭園」 に限らず、 江戸時代の歴史の研究を深めることにも貢献することが出来ると考えられる。 この考察を出発点として、 今後さらに多くの視点から研究を進めるつもりである。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
chang_ume
-
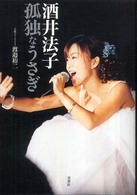
- 和書
- 酒井法子孤独なうさぎ