出版社内容情報
幕末から明治時代にかけての探検家・松浦武四郎は、蝦夷地を探査し「北海道」という名を発案した人物である。
本書は、天保7年(1836)、まだ19歳の放浪者武四郎が、四国八十八ヶ所の霊場を巡ったときの、宇和島藩領内の見聞に焦点をあてる。
領内の通過時期は、『簡約松浦武四郎自伝』の「三月土佐に入り、四月伊予国五十七番横峰寺奥の院なる石鎚山に上る」から推測して、この年の三月下旬か、四月上旬辺りと思われ、宇和島藩領での日程は、土佐藩の宿毛を通過し、四十番札所「平城山薬師院観自在寺」から四十三番札所「源光山圓手院明石寺」を打ち、大洲藩へ出た七日間であった。
その間の武四郎の足どりを自伝より再現するとともに、当時の宇和島領を記録する現存する資料より、彼の見た幕末の宇和島はどのようなものであったかを探る。
附録として「松浦武四郎が見たであろう遍路記録」を収める。
序 章 非凡人・松浦武四郎
出会い/終生、信念を貫いた松浦武四郎
第一章 『四国遍路道中雑誌』宇和島藩領の記録
武四郎が見聞した天保七年の宇和島藩/土佐との境、松尾峠/
四十番平城山薬師院観自在寺/篠山観世音寺/宇和島/願成寺
和霊大明神社/奈良山是心院等妙寺/務清山常善坊/龍澤寺
四十一番稲荷山龍光寺/四十二番一<か>山佛木寺/穴御前
四十三番源光山園手院明石寺
第二章 十九歳、青年武四郎の遍路道中に学ぶ
浄土への逃避場所、四国
直接眼で確かめる青年武四郎、念願の旅
宇和島藩領内での武四郎を解析する
札所遍路の武四郎の関心度
体力と胆力にものをいわせた武四郎の行動力
余談、松尾坂の想い出/願成寺/和霊神社/奈良山等妙寺
龍澤寺/穴御前/大師伝説/茶堂と接待と/武四郎の宇和島領内滞在日
あとがき
附録 松浦武四郎が見たであろう遍路記録
①権少僧正賢明著『空性法親王四国霊場御巡行記』
②澄禅著『四国遍路日記』
③真念著『四国遍路道指南』
④寂本著『四国遍礼霊場記』
⑤真念著『四国遍礼功徳記』
⑥『四国遍礼名所図会』
参考文献/人名索引/著者略歴
昨今、また四国遍路が見直されてきた。
平和な時代はいうにおよばず、混沌たる時代には、なおさら心の逃避を四国遍路に求めたくなるものである。自分は何か? という単純にして、しかも深奥な、自問の旅である。
青年・松浦武四郎(1818~1888)は、早くからその願望を抱きながら、19歳にしてようやく四国の旅にでた。武四郎の描いた旅の目的には、その実行年齢が、弘法大師空海(774~835)の四国で苦行された年齢と、ほとんど同じであったことでもあり、そこに魅力を感じていたのかも知れない。
まだ山岳修行者であった青年(まだ空海ともいわなかった)が、忽然、四国で大悟し、24歳のとき、それを踏まえて書いた『』で、儒教・道教・仏教を対話形式で比較し、仏教が最も優れたものである、と論破した。武四郎には、空海のそのような堂々たる覇気が、夢であったに違いない。
武四郎は、空海と同じく誰の助けも借りず、旅に出た。やがて、本州、四国、九州には飽き足らず、未開の蝦夷地へ、これも自力で旅をした。
はじめて日本地図を完成した伊能忠敬(1745~1878)も、蝦夷地だけは幕府の役人としてではなく、自費で踏破したというが、太平洋側だけに過ぎなかった。武四郎は、を含めた蝦夷全周を、三度も自費で調査し、詳細な地図と記録をのこした。
そうしたかれを幕府は、傍観できず、わざわざ役職を作って雇用し、さらに三度も、蝦夷と樺太を探索させた。それほどに貴重な人物に成長していた。
人は、誰もが生まれながらにして、旅を最高学習の場とし、多くの未知の人々と触れ合える権利を持っている。ただ、出発の号音をいつ聞くかである。先人に学ばんとするのも、それを探らんがためである。
まずは、旅をしよう。
(中略)
武四郎のようにはっきりとした目的を持ちながら旅をしよう。それが青年の特権である。
(「あとがき」より)
内容説明
幕末から明治時代にかけての探検家・松浦武四郎は蝦夷地を探査し、「北海道」という名称を発案した人物である。若い頃より各地を旅した彼は、19歳の時、四国八十八ヶ所の霊場を巡拝、宇和島藩領内を訪れている。青年・武四郎の見た宇和島はどのようなものだったか。その足どりを辿る。
目次
序章 非凡人・松浦武四郎(出会い;終生、信念を貫いた松浦武四郎)
第1章 『四国遍路道中雑誌』宇和島藩領の記録(武四郎が見聞した天保七年の宇和島藩;土佐との境、松尾峠;四十番平城山薬師院観自在寺 ほか)
第2章 十九歳、青年武四郎の遍路道中に学ぶ(浄土への逃避場所、四国;直接眼で確かめる青年武四郎、念願の旅;宇和島藩領内での武四郎を解析する ほか)
著者等紹介
木下博民[キノシタヒロタミ]
1922年6月、愛媛県宇和島市で生まれる。1940年市立宇和島商業学校卒業。住友鉱業株式会社入社。1942年出征、中国・湖北省、湖南省、東北ハルビンなど大陸を彷徨。1946年復員後、井華鉱業株式会社(住友鉱業株式会社の後身)に復職。1960年日本電気株式会社(NEC)に移籍。1983年NECの分身会社・株式会社日本電気文化センター社長。1989年退職。現在、財団法人南豫奨学会顧問(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。


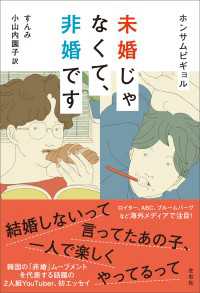

![項羽と劉邦 〈上〉 - 大人のための教科書!中国史における不朽の名作! [テキスト] 史記 1](../images/goods/ar2/web/imgdata2/47771/4777119289.jpg)




