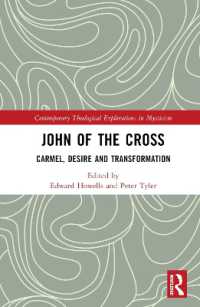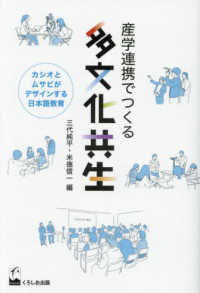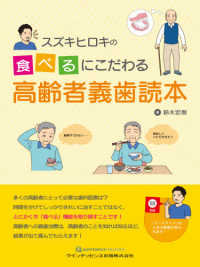内容説明
名古屋での定点観測と出版業の将来。学生時代から映画の自由上映にかかわった著者は、1974年、ちくさ正文館にバイトで入社、78年社員。それ以後40年にわたり、文学好きな経営者のもと、“名古屋に古田あり”と謳われた名物店長となる。
目次
前口上
名古屋の文化的風土
映画、演劇との関係
ちくさ正文館でのバイトと『千艸』
ブックフェアと書店の過渡期
七〇年代の社会の変貌
書店人生のスタートと同人誌運動
「全国ブランドの自立誌」としての『あんかるわ』
古田、名古屋、ちくさ正文館
「新しい歴史への旅」フェア〔ほか〕
著者等紹介
古田一晴[フルタカズハル]
1952年名古屋市生まれ。74年2月15日、ちくさ正文館書店本店にアルバイト入社。78年大学卒。78年9月正式入社(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
阿部義彦
14
論創社の「出版人に聞く」のシリーズ、今回は11となり、知る人ぞ知る名古屋の『ちくさ正文館』の店長古田一晴さんに伺います。人文書を中心に文学芸術に特化して、雑誌、学参、漫画は初めから置いていません。60から70年にかけて、前衛的な映画、演劇、音楽(アングラ)が出てきて名古屋にもその拠点として『七ツ寺共同スタジオ』ができその周辺でミニコミなどを作っていたそうです。澁澤龍彦や浅川マキのフェアを仕掛けました。本屋大賞には厳しく、大賞を読んで面白く思う人がいるのは確かだろうがその人は本当の読者にはならないと思う。2022/12/24
てながあしなが
7
千種でバイトをしているので、めちゃくちゃ近くにあったのだが、なんだかんだ初めて行ったのは大学四年の時だった。しかもその時は、人文書に強いという印象も持たなかったし、ちょっと大きい個人経営の書店、くらいにしか印象に残っていなかった。ただ、これを読むと並々ならぬこだわりを感じる。ただ、刊行がやや昔なので、昔やってたフェアなどの話に終始してたのはやや残念。もっと、この書店を貫く精神や哲学について聞きたかったな。ただ、やや時代に取り残されてる感は禁じ得ない。ここから、どうしていくのか瞠目したい。2017/08/20
ゴロウ
6
「単館」としての本屋の話やブックフェアの考えかたなど日々の仕事の参考にできそうな部分はもちろん興味深いのだが、それ以上に、名古屋の文化史におけるちくさ正文館の存在感のようなものをあらためて強く感じた。書店員としてこのお店の売場から受けた影響は大きいと自覚しているが、まだまだ奥が深いということを思い知った。「名古屋の本屋」としての矜持が随所ににじんでおり、まさしく書名通りの本である。特に名古屋で本の仕事に関わるひと、関わっていくひとは、読んでおいたほうがいい本だと思う。2013/09/08
izw
5
40年真剣に棚を整備してきた本屋の店長の心意気がすごい。図書館を批判している箇所があるが、本屋と図書館の溝の深さを改めて実感した。名古屋の本屋はほとんど行ったことがないが、今度名古屋に行く機会があったら「ちくさ正文館」を訪ねてみたい。2014/03/30
本棚葬
4
ナイス選書の本店を陰で支えていたターミナル店のことも忘れたくない。学参・児童書・コミック・雑誌の定期という経営基盤がターミナル店にあればこそ、あれだけの本棚が生まれたのだから。2025/11/18