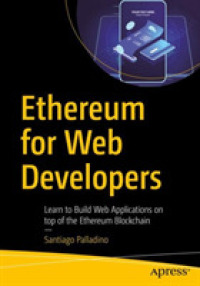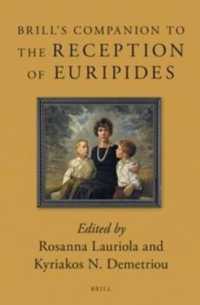内容説明
MITメディアラボ、世界のチルドレンズ・ミュージアム、学校、家庭、社会での多様な学び…自発性、好奇心、応用力が育つ「新しい学び方」の実践例を豊富に紹介!
目次
1 子どもの創造性を育むために(理想的な学び場、MITメディアラボとの出会い;新しいアイデアを形にできる環境とは?;進化する世界の教育 ほか)
2 新しい学びの場を考える・つくる(世界のチルドレンズ・ミュージアム;創造的な学びに必要な10個の「つくる」;学校での学び、家庭での学び、社会での学び ほか)
3 子どもとつくる未来―CANVAS 11年間の試みの中で(世界最大の創作イベント、ワークショップコレクション;未来を想い描く)
著者等紹介
石戸奈々子[イシドナナコ]
NPO法人CANVAS理事長/株式会社デジタルえほん代表取締役。東京大学工学部卒業後、マサチューセッツ工科大学メディアラボ客員研究員を経て、子ども向け創造・表現活動を推進するNPO「CANVAS」を設立。これまでに開催したワークショップは2000回、約30万人の子どもたちが参加。実行委員長をつとめる子ども創作活動の博覧会「ワークショップコレクション」は、2日間で10万人を動員する。その後、株式会社デジタルえほんを立ち上げ、えほんアプリを制作中(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Atsumi_SAKURADA
2
子どもたちの創造力を育む活動について、カラー写真をふんだんに織り交ぜつつ紹介した、とてもすてきな本です。「クリエイティヴ」な大人になるための本なら、いまや本屋にコーナーが設けられるほどですが、子どもについてはまだ驚くほど少ないです(たとえば、Amazonで和書の検索をかければ顕著にその差がわかります)。こうした知育で日本が諸外国に比べ後進国であるのは不思議ですが(なぜでしょうか?)、ともかくこれから強く求められる分野であることは間違いなさそうです。また、NPOの運営についても言及があればなおよかったです。2015/10/25
かおっくす
1
親の世代では,昔はオルガン,顕微鏡,プールなど学校にしかないものが多く,学校は最先端の場だった。現代はPC,テレビゲーム,大型テレビなど家庭にあるもののほうが性能がよく,いつのまにか学校が遅れた場になった,というのは,なるほどと思った。子どもの図工の展覧会もいつも作品をざっとみて終わってしまうが,その過程をドキュメント映像として見せるのはおもしろい。2015/02/03
井上岳一
1
子どもの創造力を解き放つための活動をしている著者のやってきたことをまとめた本。興味深いが、カタログみたいな本で、あまり面白くなかった。2014/05/23
Humbaba
1
例え道具が変わっても、子どもの本質までもが変化するわけではない。大切なことは、子どもを導こうとするのではなく、子どもが本来持っている能力を発揮できる場を提供してあげることである。子どもは元から才能を持っている、そのことを信じ、それを花開かせるには何が必要なのかを考え、実践することが大切である。2014/04/28
yukiko-i
0
デジタルネイティヴの子どもたちを相手に、教材の工夫次第で、子どもたちがもつ様々な力を引き出すことができると実感。従来の教育方法から転換する時期にきていると感じているので、本書で紹介されていた図工やプログラミングの事例をどうアレンジしていくか考えさせられた本。 2015/07/14
-

- 和書
- 饗宴 岩波文庫 (改版)