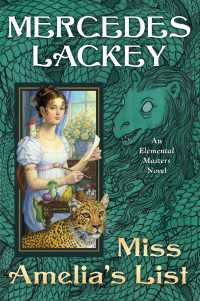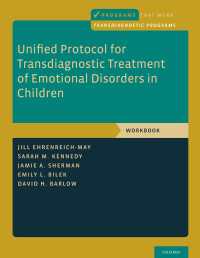出版社内容情報
1966(昭和41)年、日本の出生数が統計史上最低を記録した。原因となったのは迷信。60年に1度めぐってくる干支、丙午(ひのえうま)にまつわる俗言のためだった。高度経済成長の只中、2つのベビーブームの間にあって、たった1年、なぜ迷信がそこまでの出生減をもたらしたのか? そしてさまざまな「都市伝説」がささやかれてきたひのえうまの人生とは、実際にはどのようなものだったのか?
自身、昭和のひのえうま生まれの計量社会学者が、迷信の成立した江戸期にまでさかのぼり、周期的な拡散・浸透のタイムラインをつぶさに追いながら、ただ日本でだけ生じた特異な出生減を「社会現象」として読み解く。
内容説明
一九六六(昭和四一)年、日本の出生数が統計史上最低を記録した。原因となったのは迷信。六〇年に一度めぐってくる干支、丙午(ひのえうま)にまつわる俗言のためだった。高度経済成長の只中、二つのベビーブームの間にあって、たった一年、なぜ迷信がそこまでの出生減をもたらしたのか?そしてさまざまな「都市伝説」がささやかれてきたひのえうまの人生とは、実際にはどのようなものだったのか?自身、昭和のひのえうま生まれの計量社会学者が、迷信の成立した江戸期にまでさかのぼり、周期的な拡散・浸透のタイムラインをつぶさに追いながら、ただ日本でだけ生じた特異な出生減を「社会現象」として読み解く。
目次
第1章 江戸庶民に拡散した俗信(社会に跳ね返る迷信;始まりは八百屋お七 ほか)
第2章 明治のひのえうまと近代日本(痕跡は意外に小規模;日露戦勝の子たち ほか)
第3章 出生秘話―昭和のひのえうまの真実(「子どもは2人」の時代に;消えた赤ちゃんは16万4千人 ほか)
第4章 塞翁がひのえうま―昭和のひのえうまの人生(「レガシー」の始まり;昭和のひのえうまとはだれか ほか)
終章 どうなる令和のひのえうま(毎年がひのえうま;少子化の主因は「母集団」の縮小 ほか)
著者等紹介
吉川徹[キッカワトオル]
1966年島根県生まれ。大阪大学大学院人間科学研究科博士課程修了。現在、大阪大学大学院人間科学研究科教授。専門は計量社会学、現代日本社会論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
saga
kk
HMax
あつひめ