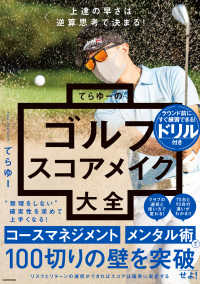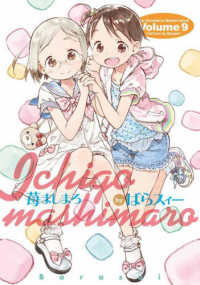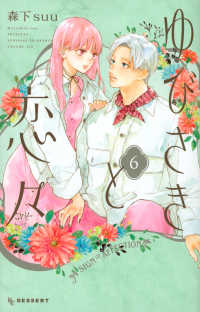内容説明
釜山にあった10万坪、500人の男だけの町「倭館」―江戸期外交・貿易の最前線。
目次
第1章 古倭館の時代(倭館のはじまり;新たな規約 ほか)
第2章 二〇〇年の日本人町(長引く移転交渉;一〇万坪の異人館 ほか)
第3章 公館としての倭館(二層式の外交;倭館外交の様子 ほか)
第4章 「鎖国」のなかの倭館貿易(金持ち大名;私貿易は花盛り ほか)
第5章 倭館に生きる(日記をつける館守;男の町 ほか)
第6章 日朝食文化の交流(倭館の日常食;朝鮮式膳部 ほか)
著者等紹介
田代和生[タシロカズイ]
1946年札幌市生まれ。慶應義塾大学大学院教授を経て、2011年同大学名誉教授。同年紫綬褒章受章。文学博士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
tohoho
0
鎖国下に幕府公認の日本人町として存在した倭館。朝鮮王朝が渡航してきた日本人を応接するための客館として都に置いたことに始まる倭館は、両国の外交実務や貿易等を現地へ赴いて行われていたことを示しており、まさに善隣友好の時代がここにあった。2015/05/19
きさらぎ
0
2002年に出版されたものの増補・復刻版らしい。草梁倭館の構造や日常生活、饗宴や応接の様子、そして江戸時代に入って確立した近世流・対馬藩主導の対朝鮮貿易の様子など、ルポ的な記述が多く、イメージを形成するのにとても参考になりました。リアルすぎてところどころ笑ってしまったほど。ただ「はじめに」には「入門書として気軽に読んで欲しい」とありますが、本当に入門レベルの私などには最初の方は知らない言葉ばかりで多少とっつきにくかったです。後半慣れて楽しく読みました。2014/07/06
ゼロコウ
0
とても面白かった。地理的な説明は初めて呼んだので。2013/06/15
hidari
0
面白かった。鎖国時代に、長崎の出島があったように、 朝鮮半島の釜山に、日本人街があった。そこに住む人々が残した書物を元に、歴史や生活を紹介した一冊。前半は、歴史的、政治的な話が殆どで、今の日本人にはあまり見られないしたたかさ、気の強さを知ることができて気持ちがいい。後半の食事や出来事については、エッセイを読んでいるようでもある。虎が出ての大騒ぎ、朝鮮人との交流、食文化の違いなどなど。特に、日本酒や味噌は評判が良かったことや、お菓子には飛び付いてしまう。学校の授業でこんな話が出てきたら面白いのになぁ。2014/10/09
つぐみ
0
鎖国時代、朝鮮半島の南端の釜山にあった、10万坪という広大な敷地を持つ倭館。朝鮮との間に起こった様々な出来事を、後日の問題処理のために意図的に記録に留め続け、その文書は20万点以上! 文書の大部分は領内治世に関するものだが、事件記録の中で面白かったのは、虎退治の模様だ。倭館に虎が侵入し大騒ぎになり、鑓や鉄砲や山刀で仕留める大捕物。仕留めた虎の1頭は内臓を抜き出して全身を塩漬けにして国元の対馬藩に送る。もう1頭は肉を庭で焼いて皆に振る舞ったという。味は、老いた牛のようで油気がなかったそうだ。皆、身体にどんな2011/11/27