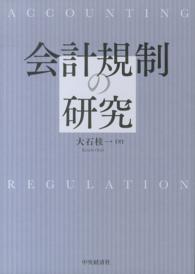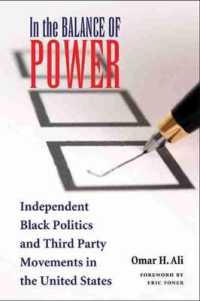内容説明
本書は、できるだけ実証的な研究をベースに、教育の場で進む階層化の実態とそのメカニズムとを解明しようとするものである。教育というスクリーンに映しだされる日本社会の階層化の動きをとらえることによって、私たちは、いま起こりつつある「階層と教育」の局面変化が、どのような影響を私たちの社会に及ぼしうるのかを知ることができるだろう。
目次
序章 問題の提起―「階層と教育」問題の局面変化
1章 流動化の時代―戦後日本の社会移動と教育
2章 メリトクラシーの時代
3章 能力主義と「差別」との遭遇―「能力主義的‐差別教育」観の社会的構成と戦後教育
補論1 平等主義のアイロニー
補論2 不平等問題のダブルスタンダードと「能力主義的差別」
4章 大衆教育社会のなかの「学歴貴族」―教育改革とエリート教育
5章 努力の不平等とメリトクラシー
6章 「自己責任」社会の陥穽―機会は平等か
7章 「自信」の構造―セルフ・エスティームと教育における不平等
8章 インセンティブ・ディバイドと未来社会の選択
著者等紹介
苅谷剛彦[カリヤタケヒコ]
1955年東京生まれ。東京大学大学院教育学研究科修士課程修了。ノースウェスタン大学大学院博士課程修了、Ph.D.(社会学)を取得。ノースウェスタン大学客員講師、放送教育開発センター助教授等をへて、現在、東京大学大学院教育学研究科教授。専攻は教育社会学、比較社会学
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きいち
37
もっと早くに読んどくんだったな。◇現在を読み解く本に必ず参照文献に挙がっている一冊。学力格差の歴史を記し、意欲の格差へ。努力は意志の賜物ではなく、それを可能にする環境=文化資本の格差の証。そして、勉強しないことを自己肯定に導く回路の存在まで浮き彫りにする。◇ここからだ、プラグマティックに現実を少しでもと願い行動するなら、これを冷徹に認識しておかねば。◇とはいえ、ここでの「努力」は、学校外での学習時間を指標としたもの。そこに突破口はある。生きる力もハイパーメリトクラシーも、この網をすりぬけられるなら肯定だ。2017/06/17
えちぜんや よーた
33
人間は、どのようなインセンティブがあれば、学習意欲が喚起されるか?という疑問から本書を読みました。前半では、かつて日本の大部分を占めていた、農家世帯の「跡取り以外の子女」が、都市での職を得るために、高学歴化したところから、問題提起を行っています。かつては、「せめて高校ぐらいは出しておかねば」という、親の思いが、学習のインセンティブを高めていました。90年代に入ると、受験競争についての認識が変化し、競争圧力を教育の世界から取り除かてきたため、学習のインセンティブが、なくなったと論じられています。 2012/10/26
山のトンネル
9
★★★★学ぶこと、趣味を謳歌することそういったものをする「動機付けの段階で格差」が生じている。そして、その格差は社会階級からくるものであることを論じている1冊。2024/07/26
Nobu A
8
苅谷剛彦先生著書8冊目。2001年初版。動機付けは学習だけに留まらず仕事や趣味と多岐に影響を及ぼす。教育社会学専門家が国内教育の変遷の中で筆者が称する「意欲格差社会」へどのように移行したか実証的研究を基に検証。厳密な枠組みでの文化資本の精査や一つのデータ(例:学習時間)を複眼的視点で捉えて厳選な仮説を打ち立て様々な考察を行う手法に感服。他方で、雑多な印象の社会学関連は相変わらず難しい。後半流し読み読了。あらゆる面での格差拡大が進行。教育の影響は計り知れない。教育はどこへ向かい、何が出来るのだろうか。 2020/10/25
客野
2
データをもとにした考察が素晴らしかった。日本の教育界が社会階層の問題とどう向き合ってきたのか(向き合ってこなかったのか)、それによって今どうなっているのかを示している。自分が今まで自明だと思っていたことを覆されるインパクトがあった。そういえば、私が高校生の時に読んだ同和問題のテキストには、このような1文があった。「同和問題に対して、『寝た子を起こすな』ではいけない」。教育のタブーに触れるこの本も、同じようなメッセージを含んでいる。2016/10/05