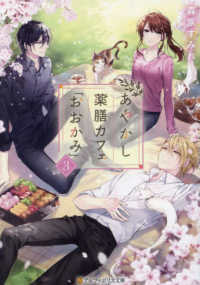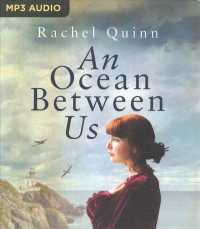内容説明
新しくラオスをとらえる社会、水田、森林、生業。
目次
ラオスをとらえる視点
第1部 社会(消えゆく水牛;民族間関係と民族アイデンティティ)
第2部 水田(水田を拓く人々;水田の多面的機能)
第3部 森林(土地森林分配事業をめぐる問題;植林事業による森の変容;非木材事業による森の変容)
第4部 生業(焼畑とともに暮らす;開発援助と中国経済のはざまで;商品作物の導入と農山村の変容)
著者等紹介
横山智[ヨコヤマサトシ]
1966年生まれ。熊本大学文学部准教授。筑波大学大学院地球科学研究科博士課程中退。博士(理学)。専門は地理学、文化生態学
落合雪野[オチアイユキノ]
1967年生まれ。鹿児島大学総合研究博物館准教授。京都大学大学院農学研究科博士後期課程修了。博士(農学)。専門は民族植物学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Akihiro Nishio
22
再びラオス本へ。タイトル通りラオスの農山村地域の話。社会、農業、林業、生業の点からまとめられる。類書に較べて珍しいのは、生業の側面。森林等で採取されるラック、カジノキ、安息香による収入がかなり大きいことがわかる。繰り返し語られるのは、ラオスにおける焼き畑農業が持続的であったこと、それが換金作物に急速に変わりつつあること。興味深いと思ったのは、お隣ベトナムのキン族と較べて、ラオ族に同化することへの敷居の低さ。仏教を受け入れて、ラオ語を喋れば、ラオになるのだという。また、少数民族との通婚率も非常に高い。2017/05/23