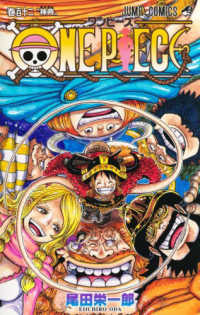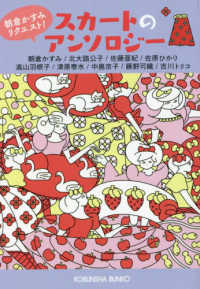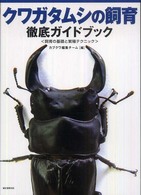内容説明
“無駄を楽しむ男”と“整理する男”。トップクリエイターが語り尽くした究極の仕事術。異なる分野で活躍する2人の“達人”が出会い、語り合う―。NHK Eテレのトークドキュメントが書籍化!
目次
第1部(遊び心溢れる職場が「くまモン」を生んだ;成功の鍵「本気」を生む秘けつ;「誕生会」が、企画の原点;企画・サービスの本質は「慮ること」;「もったいない」が発想の源;「サービス精神」と「サプライズ」;「結果」を出すことの重み;小山薫堂の仕事場「オレンジ・アンド・パートナーズ」オフィス;佐藤可士和の仕事場「サムライ」オフィス)
第2部(「違い」が浮き彫りになる達人達;「整理する男」の仕事場とは;「意思決定者」と仕事をする;「整理する」というブランディングの効果;会社ブランディングと、個人のブランディング;カリスマ経営者が佐藤可士和を大絶賛するワケ;企画の達人を悩ませた仕事とは;日本という国をブランディングする;達人達の「化学反応」)
著者等紹介
小山薫堂[コヤマクンドウ]
放送作家、脚本家。「オレンジ・アンド・パートナーズ」代表、東北芸術工科大学デザイン工学部企画構想学科長。1964年、熊本県生まれ。日本大学芸術学部在学中に放送作家としての活動を開始し、ユニークなヒット番組を連発。脚本を手がけた映画『おくりびと』(2008年)ではアカデミー賞外国語部門賞を受賞した。熊本県地域プロジェクトアドバイザーとして「くまモン」を生み出し、京都の料亭「下鴨茶寮」の亭主、日光金谷ホテルの顧問を務めるなど、活動の幅を広げている
佐藤可士和[サトウカシワ]
アートディレクター、クリエイティブディレクター。「サムライ」代表、慶応義塾大学特別招聘教授、多摩美術大学客員教授。1965年、東京生まれ。多摩美術大学卒業後、博報堂を経て2000年に「サムライ」を設立。06年にはファッションブランド・ユニクロの世界進出に際し、ニューヨーク旗艦店のブランディングを担当。「セブン‐イレブン」、「今治タオル」のクリエイティブディレクターも務め、国立新美術館のシンボルマークデザインからミュージアム、病院、幼稚園のプロデュースまで仕事は幅広い(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
tuppo
Megumi Ichikawa
okatake
くりす
よちよち