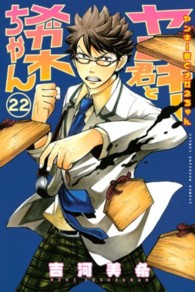出版社内容情報
春夏秋冬、わたしたちはいろいろな風に吹かれながら生きています。たこ揚げや風車など、風の力を利用しているものもたくさんあります。いったい風はどうやって吹いているのでしょう。どこから来てどこへ行くのでしょう。風を生み出すのは、つめたい空気とあたたかい空気のながれです。小さなそよ風も、大きな台風も、基本のしくみはおなじなのです。地球上のさまざまな風の動きをひもといていきます。
著者等紹介
吉野正敏[ヨシノマサトシ]
1928~2017。東京都に生まれる。東京文理科大学地学科卒業。理学博士
夏目義一[ナツメヨシカズ]
1954年、神奈川県に生まれる。日本大学芸術学部卒業。動物画を中心に、ナチュラルアート全域を制作テーマとする(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
☆よいこ
93
科学読み物。分類451。まわりを海で囲われいくつもの山脈はしっている日本列島は「風の国」▽地表近くを吹いている風ははだで感じることができるが、上空の高いところをふいている風は雲を見るとわかる。木を見てもわかる。風は空気の流れ。横ではなく縦に動く空気は風とはよばず気流という。地球全体をおおう風の流れがある。台風のしくみ。風の力をいちばんよく使ったのはヨーロッパ16世紀から19世紀。もし風がふかなかったら大変▽初出1990年。傑作集2025.4刊2025/07/07
明るい表通りで🎶
41
風は、地球上の生き物にとって、かけがえのない、どうしても必要なもの。赤道付近の熱を、貿易風、偏西風、極編東風とリレーされ、地球全体に行き渡らせている。ジェット気流も。富山県八尾の「風の盆」。風をまつる行事として、風の神おくりと、先祖の霊を供養する盆踊りがいっしょになったお祭り。2025/05/12
kawa
29
風によって、赤道付近の太陽から受けた熱が地球全体をおおい、私たちの場所を住みやすいところに変えていると言う。かけがのない、どうしても必要な風について考える。早朝から雨で日課の散歩が出来ないとき、ゆったりコーヒーを飲みながら眺めるのに最適書。(図書館新刊書コーナーから、小学生中級向き)2025/06/03
mntmt
4
いつも不思議に思ってたことなので読んでみた。少しわかった。2025/06/14
サト
3
風、雲、台風の作られ方について。 赤道の熱がそのまま止まっていたら熱くて住めず、他の地域は寒冷化してしまう。 熱が移動することで地球全体がほどよく暖かく、冷めることができ、人が住める星になっています。 台風・ハリケーンの被害は昔からありますが、その仕組みから風の恵みを感じることができます2025/06/20