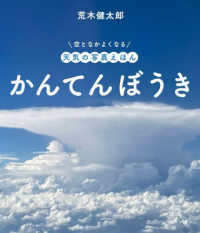出版社内容情報
植物といえば、緑色の葉っぱを思い浮かべますよね。それは、緑色の色素があるからです。この色素があることで、多くの植物は光合成をして、日光から栄養を作り出すことができるのです。ところが、この色素を持たず、キノコなどの菌を「食べて」生活する植物たちがいます。光合成をやめた植物たちは、色や形も風変わりなものばかり。彼らのちょっと変わった生活をご紹介します。
内容説明
光合成をしない!?奇妙な植物たちの、ちょっとずるい生存戦略。小学中級から。
著者等紹介
末次健司[スエツグケンジ]
1987年、奈良県生まれ。2010年、京都大学農学部卒業。2022年より神戸大学大学院理学研究科教授。同大学高等学術研究院卓越教授を兼任。専門は、日本の生物多様性を活かした植物、菌類、昆虫のナチュラルヒストリーの研究。主に、光合成をやめた植物である「菌従属栄養植物」の生態を研究し、「キリシマギンリョウソウ」や「妖精のランプ」と呼ばれる「コウベタヌキノショクダイ」など、多くの新種を発見(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kinkin
97
タイトルが面白い。植物は光合成するのが当たり前なのに。それをせずに他の生き物を「食べて」生活している・食べると言っても大口を開けて食べるのではないのだが。世界的には1000種くらいいるとか。根に入ってきたキノコやかびを消化してしまう。この植物のことは、うっすら知ってはいたが実際に見たことがないのでそれが残念。ギンリュウソウは割と見つかりやすいそうだが・・・もう少し調べてみたいと思った。児童書とはいえ大人にも十分な内容。図書館本2025/09/07
☆よいこ
91
分類471。たくさんのふしぎ傑作集。「植物」をやめた植物=光合成をやめた植物「菌従属栄養植物」▽光合成をしないので緑以外のカラフルなものが多い。[①キノコを食べる]キノコと光合成をする植物のネットワークに横入りして、キノコの菌糸を消化する[②花粉の運び方]自家受粉。キノコに依存する[③種の運び方]昆虫に食べられる▽最初キノコのことかと思って手に取ったら、キノコに寄生する植物だった。ギョリンソウの名前くらいしか知らんかった。新種を発見したいなら穴場グループらしい。2023年発行2025/03/14
サンダーバード@怪しいグルメ探検隊・隊鳥
71
(2025-40)【図書館本-28】児童書だったけど、なかなか面白い。通常の植物は「光合成」を行い、太陽光と二酸化炭素から必要なエネルギーを作り出す。だがそれをやめて、他の植物に寄生することによって栄養素を摂取するように進化した植物がいる。私はギンリョウソウくらいしか見たことが無かったけれど、こんなにたくさんの種類がいるのを知って驚いた。光合成をやめて他人に寄生することにより、光の当たらない森の奥深くでも生育できるようになったこれらの植物たち。これは果たして進化なのか、生存競争からの逃避なのか?★★★+2025/03/15
やいっち
70
「(前略)光合成をやめた植物たちは、カラフルで変わった形のものばかり。種類もさまざまです。小さくて目立ちにくいものが多いですが、じつは日本中どこでも、身近な森にひっそりと生息しているんですよ。どうして彼らは光合成をやめてしまったのか? どんな花を咲かせ、どんな生きものに花粉や種子を運んでもらっているのか? 暗い森のなかで生きのびるための、彼らのたくみな作戦をときあかします。」小学生対象の図鑑。うん、我輩向き。植物の生存戦略の巧みさ、必死さ。2025/05/25
shikashika555
44
植物と動物の違いがわからなくなる。 面白い! こんな生存戦略をとっている植物があるんだ。 食虫植物や粘菌は知っていたが、他にも光合成をしないで生きている植物があるんだね。 そしてそれは、やはり植物としては「イレギュラー」な生き方で。だから豊かな森にしか生息し得ない。 カラフルな写真が豊富で見ても楽しめる。 自然のものの写真を見るたびに、こんな作り物のような色を自然の生物が持っていることに驚く。2025/09/01
-
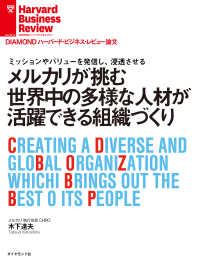
- 電子書籍
- メルカリが挑む世界中の多様な人材が活躍…