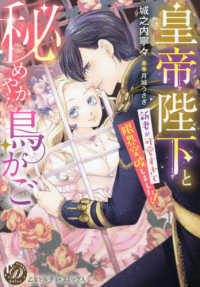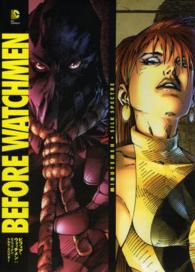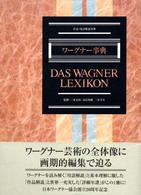内容説明
乱世の「座右の書」「指南書」“ロングセラー”待望の新装版!!東洋学への深い造詣と、一流経営者との肝胆相照らす交わりから、初めて発掘された“叡智の核心”。現代を生きぬく経営者・リーダーの条件を問う伊藤肇のライフワーク。
目次
第1章 原理原則を教えてもらう師をもつこと(「修己治人」のメルクマール;「偉大なる常識」の行い難さ;治乱興亡の摂理;喜怒哀楽の原理原則 ほか)
第2章 直言してくれる側近をもつこと(側近登用の原則;心友に学ぶ人生の知恵;直言を生かす人間関係;直言の条件 ほか)
第3章 よき幕賓をもつこと(幕賓の資格)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
金吾
20
著者独自の視点は然程あるように感じませんでしたが、さまざまな人間が述べている箴言や標語が大量に記載されているため、自分の考えや視点を整理するのにいい本だと感じました。2021/08/12
とみやん📖
11
昭和の本だが、味わいが深い。 城山三郎→伊藤肇→安岡正篤と読書でいざなわれたが、人物や人生を見つめるにはとても良い系譜だと思う。伊藤肇は、経済ジャーナリストとして多くの財界人と交流があった人とのことだが、深みや含蓄のある言葉を紹介してくれる。傲岸不遜で鼻につく俗っぽさもまた魅力の一つかもしれない。ふと行き詰まったときに再読したい本。2019/11/13
オーシャン
8
「帝王学」とは、絶対的な身分の格差があった時代に、生まれながらに人の上に立つことを運命づけられた人のための学問として発達したものとの認識でした。しかし本書には、これは「人間学」であると書かれています。どのように人に仕えて、どのように人の上に立つかを、論語などの中国の古典や日本の財界の先人達の実例を交えて、解説されています。原理原則を学ぶこと、側近としてどのように提言するかなどビジネスでどのように人間関係を構築し、自分を活かすかの指南書です。まさに、「現代の帝王学」であり、レベルの高いビジネスマナー本です。2016/07/02
KAZOO
7
これはむかしプレジデントという雑誌の掲載されていたものを1冊の本にしたものです。雑誌のころに読んではいたのですが若かったためあまり興味がなく印象には残っていません。様々な明治時代や昭和の初めの政治家などを題材にして中国の古典を繙きながら指導者の在り方は、ということを説いているのですが最近はあまりはやらないのだと思います。中国の古典などが出てくるので私はこのような引用の仕方もあるのかと感心しています。2014/02/06
サミー
5
ぼくはていおうにはなれない2017/09/30
-
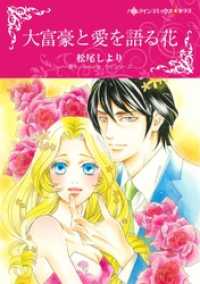
- 電子書籍
- 大富豪と愛を語る花【分冊】 3巻 ハー…