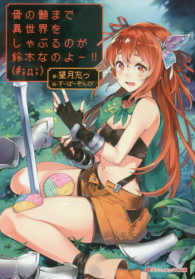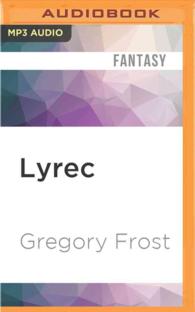出版社内容情報
金閣・銀閣を擁する大本山相国寺。貴重な寺内史料から蘇る、時代の変化に立ち向かい、法灯を守り続けた僧侶たちの苦悩と努力の歩み。現在の日本仏教各宗派は、近代的な教団組織によって運営されている。
そのような組織は、いつ、どのように誕生したのか。
「教団」の成り立ちと変遷に焦点を合わせ、新視点で捉え直す日本仏教史。
大本山相国寺で行われた全10講の講義録
金閣寺・銀閣寺を山外塔頭として擁する大本山相国寺には、江戸時代から昭和に至る寺の歴史を克明に記録した史料が存在する。
本書ではそれらの史料に基づき、時代の変化に立ち向かい、法灯を守り続けた僧侶たちの苦悩と努力の歩みを蘇らせる。
----------------------------------
「十大宗派」を始めとする仏教教団は、本山にあたる寺院に宗務本所を置き、宗派の長たる管長の下に宗務総長を中心とする事務組織を構成していることが一般的です。また、宗派の運営方針を決定するために宗議会が組織され、各地域の末寺から選挙で選ばれた宗議会議員によって様々な議論が行われています。
このように、仏教教団の運営が形の上では近代化されていることは、あまり知られていない事実でしょう。大陸からの伝来以来、長い歴史を持つ日本の仏教が、近代的教団組織をいつ、どのように形成させたのか。それが本書で問いたいテーマです。
(中略)
これまでの仏教史は、各宗派の宗祖や開山(寺院を創建した僧侶)の事跡を論じることが主流でした。しかし、現代を生きる僧侶にとっては、自身が所属している教団の組織が形成された江戸時代以降の歴史を捉えることが重要な意味を持つはずです。また、僧侶以外の寺院に関係する人々にとっても、教団の成り立ちを知ることは現代仏教への理解を深めるうえで有意義なことであると考えます。本書において、近代への展開に重点を置いた新たな仏教教団論を切り開きます。
(「はじめに」より)
----------------------------------
※本書は大本山相国寺に設置されている相国寺教化活動委員会の研修会講義録『相国寺本山所蔵古文書の全容と新出史料の紹介』、『宗門と宗教法人を考える─明治以降の臨済宗と相国寺派─』、『『相国寺史料』を読む─江戸時代の相国寺と山内法系─』を加筆・修正のうえ、再編集したもの。
凡 例
はじめに
第一部 室町・戦国時代の相国寺
第一講 相国寺と北山第の開創
1 足利義満による相国寺の創建
2 相国寺大塔と北山第の建築
第二講 東山山荘と鹿苑僧録・蔭凉職
1 東山山荘の造営
2 鹿苑僧録と蔭凉職
第二部 江戸時代の相国寺
第一講 江戸時代前期における門派の形成─西笑承兌と常徳派
1 江戸禅宗史研究の視点
2 江戸時代における門派
3 常徳派の成立
4 豊光寺・大光明寺輪番争論一件
5 輪番争論その後
6 まとめ
第二講 安土桃山?江戸時代中期における大智派と光源院・慈照寺
1 安土桃山時代における大智派
2 園松寺天外梵知後住一件
3 大智院輪番争論一件
4 慈照寺山林争論一件
5 慈照寺祖桓擯斥一件
6 まとめ
第三講 江戸時代中期における相国寺山内の動向─山門修理と天明大火
1 困窮する塔頭
2 山門修理と富くじ興行
3 天明の大火
4 まとめ
第四講 江戸時代後期における白隠禅の浸透と門派の衰退
1 禅宗の歴史と白隠禅
2 僧堂再興の発端と白隠禅の浸透
3 相国僧堂の成立
4 伽藍の復興
5 常徳派による輪番住持制の破綻と鹿苑寺の混乱
6 まとめ
第三部 明治?昭和期の相国寺
第一講 国家神道体制の形成と相国寺派の動向
1 明治国家の成立と神道国教化政策
2 明治初期における臨済宗・相国寺派の動向
3 神道国教化政策の破綻と国家神道体制の形成
4 まとめ
第二講 宗派財政の窮乏と「臨済宗相国寺派紀綱」の編纂
1 相国寺派財政の悪化
2 国泰寺派の独立
3 「臨済宗相国寺派紀綱」の編纂
4 まとめ
第三講 戦時体制における臨済宗と相国寺派
1 大正から昭和にかけての世相
2 臨済宗七派聯合布教団の発足と臨黄合議所の設置
3 宗教団体法の制定と臨済宗の合同
4 宗教団体法・臨済宗合同の諸影響
5 臨済宗と相国寺派の戦争協力
6 まとめ
第四講 宗教法人法の成立と古都税反対運動
1 宗教法人法の成立
2 金閣の焼失と再建
3 銀閣寺事件
4 文化観光施設税・文化保護特別税の導入
5 古都保存協力税反対運動の経緯
6 古都税の証言
7 まとめ
おわりに
あとがき
主要参考文献
写真一覧
相国寺略年表
藤田和敏[フジタカズトシ]
著・文・その他
内容説明
「教団」とは何か?金閣・銀閣を擁する大本山相国寺の歴史から、その成り立ちを考える。
目次
第1部 室町・戦国時代の相国寺(相国寺と北山第の開創;東山山荘と鹿苑僧録・蔭凉職)
第2部 江戸時代の相国寺(江戸時代前期における門派の形成―西笑承兌と常徳派;安土桃山~江戸時代中期における大智派と光源院・慈照寺;江戸時代中期における相国寺山内の動向―山門修理と天明大火;江戸時代後期における白隠禅の浸透と門派の衰退)
第3部 明治~昭和期の相国寺(国家神道体制の形成と相国寺派の動向;宗派財政の窮乏と「臨済宗相国寺派紀綱」の編纂;戦時体制における臨済宗と相国寺派;宗教法人法の成立と古都税反対運動)
著者等紹介
藤田和敏[フジタカズトシ]
1972年、愛知県に生まれる。1996年、立命館大学文学部史学科卒業。2005年、京都府立大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得満期退学、博士(歴史学)。大本山相国寺寺史編纂室研究員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-

- 電子書籍
- DX時代の部下マネジメントー「管理」か…