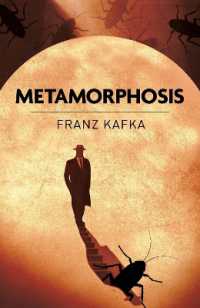内容説明
神仏習合は中世社会にどう定着していったのか?儀礼資料を読み解くことで、神仏習合がつねに仏教儀礼を通じて展開したことを明らかにする。
目次
中世宗教儀礼研究の射程―神仏をめぐる思想と表現
第1部 解脱房貞慶の信仰と儀礼(貞慶の笠置寺再興とその宗教構想―霊山の儀礼と神仏;『春日権現験記絵』の貞慶・明恵説話とシャーマニズム―憑依・託宣説話から講式儀礼へ;貞慶『春日権現講式』の儀礼世界―春日社・興福寺における中世神話の生成;貞慶撰五段『舎利講式』の儀礼世界;貞慶撰五段『舎利講式』の展開)
第2部 中世律僧の信仰と儀礼(貞慶『発心講式』と玄縁『礼仏懴悔作法』をめぐって―本覚思想と懴悔の儀礼;南都戒律復興における受戒儀礼と春日信仰の世界―律僧とシャーマニズムの視点;春日神に抗う南都律僧―死穢克服の思想;叡山律僧の受戒儀礼と山王神―本覚思想およびシャーマニズムとの関係から)
第3部 中世真言密教の信仰と儀礼(頼助『八幡講秘式』と異国襲来―鶴岡八幡の調伏儀礼と中世神道説;久我長通『八幡講式』と南北朝争乱―石清水八幡の密教修法と本地説の展開;死穢と成仏―真言系神道書に見る葬送儀礼;摂関家の南円堂観音信仰と春日神―秘説の生成と密教儀礼をめぐって)
著者等紹介
舩田淳一[フナタジュンイチ]
1977年鳥取県生まれ。2000年龍谷大学文学部卒業、2003年佛教大学大学院文学研究科仏教文化専攻修士課程修了、2008年同博士課程修了。首都大学東京オープンユニバーシティ講師・武庫川女子大学関西文化研究センター学術フロンティア研究員を経て、仏教大学・摂南大学非常勤講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。