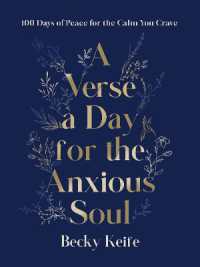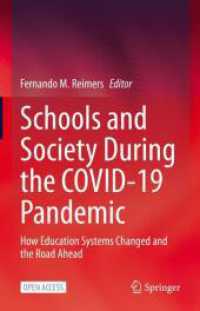目次
第1部 日本刀の歴史(直刀時代(神代と上古代)
平安朝時代(大同~寿永) ほか)
第2部 日本刀鑑定の基礎知識(刀身各部の名称;刀剣の区分 ほか)
第3部 日本刀の鑑定(五箇伝;古刀と新刀の相違)
第4部 全国刀工の特徴と系統(古刀の部;新刀の部)
第5部 日本刀の鑑賞(総論;刀剣鑑賞の予備知識)
著者等紹介
常石英明[ツネイシヒデアキ]
高知県高知市生まれ。昭和7年頃から上村独笑、小野賢一郎両氏に古陶磁を学び、当時の東京世田谷美術同好会幹事などを務める。また、大学在学中より、本阿弥光遜の日本刀研究会に入り、特別の指導を受ける。四谷刀剣研究会および世田谷日本刀剣研究会等の幹事を務めながら、刀剣、古陶磁、古書画等の研究をかさねる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
六点
2
なんというか、特徴を誇張したイラストで書いてあるからわかりやすいけども、「匂い出来」と「沸出来」の辨別から五箇伝そして各筋の特色と、刀剣鑑定の道は果てし無く覚えることばかりと思い知らされる。それだけ奥が深い世界なのだ。2016/10/27
眉毛ごもら
0
日本刀の鑑定に関する本である。鑑定に関する本であるので品位がある、上作であるという言葉が多用される。逆に鑑定価値の低いものについては田舎臭いだの品がないだの下作だの極めつけに美術的価値はない、とまで言われるのである。その言葉に耐えられる人だけ読んでみましょう。私は自分の目で見ていいと思った刀がいい刀なので知らん刀でもボロクソ言われるとちょっと辛いところがあった。初版は2016年だが昭和の本の復刻と思われ大包平が池田家所有、参考文献が昭和37年のものが最後だったりちと情報が古い可能性があるのでそこも注意だ。2021/05/16