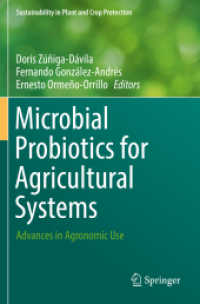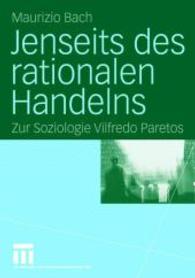内容説明
「礼楽」をキーワードに教養文化の展開と変容を考察した国際シンポジウムの成果。「詩書礼楽」の重要性を説いた孔子―。その教えと伝統を共有する東アジア文化圏―。
目次
1 中国の礼楽(中国古代の飲食文化と礼楽―孝子の三道をめぐって;『荀子』における礼楽思想の分析;王安石から朱熹へ―宋代礼学の展開 ほか)
2 朝鮮の礼楽(朝鮮時代の「儒教」と「楽」について―思想史からの一試論;朱子学における理学的礼楽論と朝鮮;現実と原則の調和を追求した退渓の礼論 ほか)
3 日本・琉球の礼楽(荻生徂徠一門の音楽嗜好とその礼楽観;日本における明楽の受容;守礼の邦の音楽)
シンポジウム総合討論 東アジアにおける「礼」と「楽」―東アジア共通の教養として
著者等紹介
小島康敬[コジマヤスノリ]
1949年、岐阜県生まれ。学習院大学大学院人文科学研究科博士課程退学。国際基督教大学教養学部教授。日本思想史専攻(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きさらぎ
7
2010年にICUと韓国で開催された国際シンポジウム「東アジアにおける「礼」と「楽」-東アジア共通の教養として-」の発表をまとめた論考集。主催は『徂徠学と反徂徠』を書かれた小島康敬氏。中国、韓国、日本と節を分けてそれぞれの3~5本の論考を載せ、ラストにはシンポジウムの対談を収録。荀子の礼楽観、王安石と朱熹、徂徠学における礼楽など、非常に興味深かった。仁の孟子と礼の荀子とも言われ、法家との親和性が言われる荀子があくまで儒者であったのは、礼の根本に楽と人情を見ていたからなのかもしれないと思ったり。2019/03/16