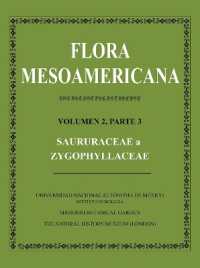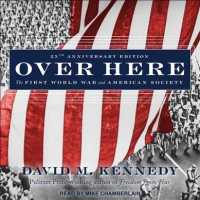内容説明
中世と近世の端境期において、治道の究明を目指して幕藩体制下の武家社会に独自の神道理論を広めた吉川惟足(1616‐1694)―吉田神道の道統継承者にして吉川神道の提唱者であった惟足の思想を、信仰の拠としての神典(『日本書紀』神代巻)の役割と、神々と人とのつながりを媒介する詠歌の役割から解明し、神道の言葉化の一端を探る。
目次
第1章 吉川惟足の『日本書紀』尊重論
第2章 吉川惟足の混沌と未生已生論―神代巻冒頭の解釈について
第3章 吉川惟足の道統継承問題の再考察
第4章 吉川惟足の葬祭論の一考察―保科正之の神葬祭をめぐって
第5章 吉川惟足における神籬磐境の伝の要諦
第6章 吉川惟足の八雲神詠理解と詠歌に関する一考察
第7章 吉川惟足の神語の理解と詠歌
第8章 吉川惟足と山崎闇斎の神代巻解釈の相違についての一考察
第9章 吉川惟足に見る中世と近世神道思想の端境期
著者等紹介
徳橋達典[トクハシタツノリ]
1964年、東京都生まれ。國學院大學大学院文学研究科博士課程修了。博士(神道学)。現在、共同通信社ビジュアル報道局写真部次長。専攻―神道学・神道史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。