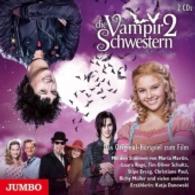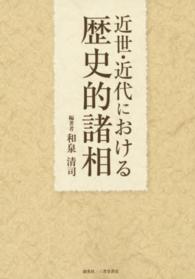内容説明
知・情・意という、古くから言われる心の働きのうちの「情」が感情にあたる。感情によって古代以来人間が考え行動してきた蓄積を考えるとき、それは歴史であり文化の問題となる。人間の心のもっとも重要な働きである「感情」のしくみを考察した日本人論。
目次
第1章 “感情”をどう捉えるか(“感情”の問題とは何か;“感情”を指し示す言葉について ほか)
第2章 “感情”と心の外部―古代的世界観の場合(古代における「情」と「心」;古代的世界観における“感情”―自然など「心」の外部との繋がりについて)
第3章 身体と繋がる“感情”―中世仏教の場合(中世無常観における“感情”の問題―「煩悩」と「菩提」;「花は愛惜にちり、草は棄嫌におふるのみなり」―道元 ほか)
第4章 身体から分離する“感情”―近世思想の場合(「恋の手本」と「忍恋」;人間関係における「敬」と「愛」―近世儒教 ほか)
第5章 “感情”の行方―近代的自我の場合(「人間の霊魂を建築せんとするの技師」―北村透谷;「霊魂ののすたるぢや」―萩原朔太郎 ほか)