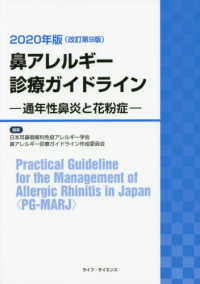内容説明
科学的管理。その出現は人類史的出来事である。それは、どのようなものであり、どのように発展し、現在に到っているか。それは、人類を自然世界の住人を人工的世界の住人に、たった百年で変えた。人間は、科学的管理の成果の驚異的機能性を享受しながら、それが意図せずして惹き起した負の随伴的結果である自然破壊、社会不安・人間性喪失の増大の危機に遭遇している。ここに、管理学の巨人たちの位置と意味は明かされ、危機克服の方途が示された。
目次
序章 管理とは何か―方法と体系
1 科学的管理の創始―F.W.テイラー
2 管理の真髄―M.P.フォレット
3 現代管理論の基礎―C.I.バーナード
4 コーポレート・ガバナンスとしての管理―P.F.ドラッカー
補章 管理の科学の思想
終章 科学的管理の世界
著者等紹介
三戸公[ミトタダシ]
1921年山口県に生れる。1949年九州大学法文学部卒。現在、立教大学名誉教授・中京大学名誉教授。経済学博士。著書に、『公と私』(未来社、1976年、毎日出版文化賞受賞)、『財産の終焉―組織社会の支配構造』(文真堂、1982年、経営科学文献賞受賞)、『家の論理・1 日本的経営論序説』(文真堂、1991年、経営科学文献賞受賞)、『家の論理・2 日本的経営の成立』(文真堂、1991年、経営科学文献賞受賞)など
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
1
評者は、食糧生産「管理」学という研究室にいたことがある。この管理ということばには抵抗があった。経営学の中で、管理ということばの意味を考える本だが、経営資源としての人、物、金、情報の管理だろうが、バーナードは協働を言っているのでかねてから評価していた人。「組織の社会学」(141ページ)を志向していたのが共感できる。経営社会学という分野があるのかもしれない。経済人を脱して、「全人」仮説を提起したことが重要な肝。個人主義と集団主義の統合(153ページ)。全人はラスキンも言っていたので、トータルな人間把握が大切。2012/10/05
sidus
0
超えていない。己の学習内容をまとめ、己の関心を付け足しただけだ。企業は環境問題という目的外の生産物についても責任を負えという。しかし企業が存続を求めるなら対応せざるを得ない。企業は顧客によって成立するからだ。だが、企業が生み出した目的外の環境破壊、従業員の扱いを、企業や業界が自らリストするべきだとは思う。2009/03/31
-
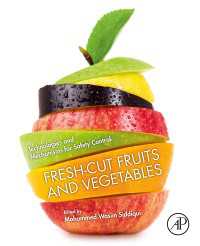
- 洋書電子書籍
- Fresh-Cut Fruits an…
-
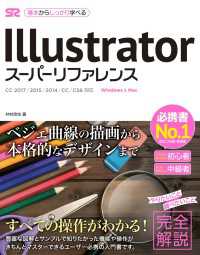
- 電子書籍
- Illustrator スーパーリファ…