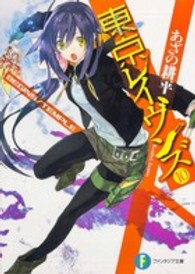出版社内容情報
ベトナム国家という主体は、その「近代化」、「グローバル化」、「先進国化」に向け、その経済・社会・政治システムを世界に開いてきた。先行する東アジアそして東南アジア諸国の発展プロセスを目標にする-「絶対化」-とともに、自国にあった形で、それを「相対化」―「中進国化」-してきた。そして、日越間の経済的相互依存関係という点では、日本政府や日本企業、また、組織における人材や個人の果たした役割も小さくはない。それは、例えば、日本政府の開発協力であり、日本企業のベトナムへの投資であり、また、諸組織に属しているかいないかを問わず、経済活動やそれにとどまらない教育・文化・社会活動を行ってきた個人の果たした役割を容易に想像することができる。また、ベトナムからみれば、日本を含む、海外企業からのベトナムへの投資の状況とそれを受け入れるベトナム側での法的整備やインフラ整備、人材育成などが重要なテーマとなっていた。そして、政府、企業等における汚職などの防止を含む、広義の「経済安全保障」も重要なテーマであった。ベトナムの未来をさらに切り拓いていくための現状の課題について、「経済安全保障」という側面からも考察していくことも重要な課題としている。こうした課題の検証を行ったのが本書である。
内容説明
中国に代わる生産拠点・ベトナム経済の行方は?1990年代以降の経済発展を検証し、外国直接投資(FDI)等の歴史や日越企業の経営・人材戦略とケーススタディから未来を展望する。
目次
第1部(日本のODA政策とベトナム;「アジアの奇跡」と経済発展―1990年代のベトナムの「離陸」;1990年代のベトナムの経済発展と日本・ベトナム貿易―繊維産業への注目;フォーク株式会社の1990年代の取り組み―縫製業のケース;外国直接投資(FDI)は国民生活に役立つか?)
第2部(巨大都市ホーチミン市の変貌とFDI;ベトナムの産業政策 IT化への歩み;ベトナム企業の新展開と課題―企業法の変遷と「天満ベトナム事件」に着目して;ビングループのスマホ事業への進出と撤退;Tiger Vietnamのケース―ベトナムでの人材育成への取り組み;ベトナムにおけるガス供給機器メーカーのグローバル戦略―矢崎総業、I・T・O、桂精機製作所(カツラベトナムKVN)を通して
ベトナムの未来)
著者等紹介
藤江昌嗣[フジエマサツグ]
明治大学経営学部専任教授、明治大学MOS(マネジメント・オブ・サステナビリティ)研究所所長。釧路市生まれ、帯広市を経て、旧浦和市。京都大学経済学部卒業。日本鋼管(株)、神戸大学大学院を経て、岩手大学人文社会科学部専任講師、東京農工大学農学部助教授、明治大学経営学部助教授。1993年4月明治大学経営学部教授。ポートランド州立大学客員教授(2000~2002年)。1994年3月京都大学博士(経済学)。戦略研究学会会長(2015~2023年)を経て、現在顧問。専攻は統計学・経済学
杉山光信[スギヤマミツノブ]
東京大学文学部卒業。東京大学新聞研究所教授を経て、明治大学文学部教授を務め、2015年に退職
上田義朗[ウエダヨシアキ]
流通科学大学名誉教授・合同会社TET代表社員。大阪府生まれ。神戸大学大学院経営学研究科博士後期課程満期退学(1983年)後、日本証券経済研究大阪研究所研究員を経て、流通科学大学商学部助教授・教授。その間にアジア経営学会会長、日本ベトナム経済交流センター副会長など歴任
東長邦明[トウナガクニアキ]
明治大学MOS(マネジメント・オブ・サステナビリティ)研究所客員研究員。戦略研究学会常任理事・事務局長。医療法人財団医親会顧問。三重県生まれ。京都大学経済学部卒業。東京海上ホールディングス(株)勤務(アジア地域本部取締役CIO、欧州・北米・東南アジア・中国各地域本部取締役・監査委員)を経て現職。1999年より明治大学兼任講師。2008年より明治大学ビジネスイノベーション研究所客員研究員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
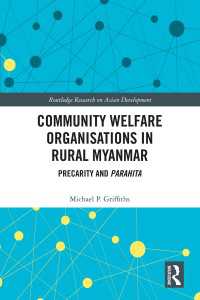
- 洋書電子書籍
- Community Welfare O…
-
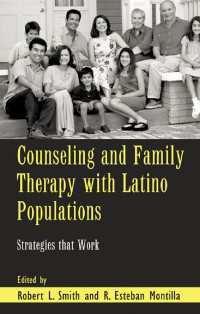
- 洋書電子書籍
- Counseling and Fami…