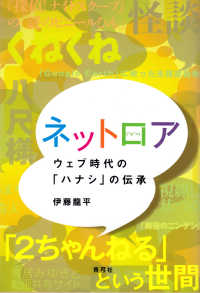内容説明
新聞・テレビはなぜ「うそ」になるのか。わかりやすさという罠、正しさという誤謬。「私は常に正しい」の虚構を見破れ!異端の愉悦をもって正統を斬る戦闘的メディア論。
目次
第1章 オウム事件―メディアと社会の分水嶺
第2章 メディアは社会の合わせ鏡である
第3章 客観中立報道はあり得ない
第4章 メディア論とジャーナリズム論を峻別すべし
第5章 メディアは市場原理でしか動かない
第6章 国家権力の監視こそメディアのレゾンデートル
第7章 上杉隆=メディア論
第8章 未だリテラシーを語る段階にあらず
著者等紹介
森達也[モリタツヤ]
1956年広島県生まれ。86年、テレビ制作会社に入社。デビュー作は小人プロレスのテレビドキュメント作品。以降、報道系、ドキュメンタリー系の番組を中心に数々の作品を手がける。98年、オウム真理教の荒木浩を主人公にするドキュメンタリー映画『A』を公開。2001年、続編『A2』が山形国際ドキュメンタリー映画祭で特別賞・市民賞を受賞。現在は執筆が中心。近著に、第33回講談社ノンフィクション賞を受賞した『A3』(集英社インターナショナル)などがある
上杉隆[ウエスギタカシ]
1968年福岡県生まれ。ホテル、テレビ局、衆議院議員公設秘書、ニューヨーク・タイムズ東京支局取材記者などを経て、フリージャーナリストに。政治、メディア、ゴルフなどを中心に活躍中(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
魚京童!
11
壊れちゃいかんのか。2015/11/26
黒頭巾ちゃん
6
昨今のマスコミついて事件を絡めて言及しています。マスコミを2つに分けることができます。ポピュリズムに則りビジネス優先の「メディア」と事実や真実など私見をも含めて表現する「ジャーナリズム」。日本では、スポンサーを優先したり、記者クラブの横並びな状況から「メディア」が横行しています。逆に欧米では、「間違えることが前提」ということで、ジャーナリズム中心です。それはきっと、“キリスト教文化”が根付いているからでしょう。思考停止のこの国で、事実のみを抽出し自己判断するしかまともな意見は言えないようです2012/11/08
YOS1968
5
ドキュメンタリー作家・映画監督の森さんと、ジャーナリストを辞めた上杉さんの対談を収めた本である。オウム事件のドキュメンタリーでメディアの思考停止の問題提議をした森さん。記者クラブの閉鎖性からメディアの無謬性を論じた上杉さん。この二人のことだからさぞかし盛り上がると思ったのだが、そこまで燃え上がりません。ちょっと根本のスタンスが違うのではないかと感じた。2012/11/09
ぽんくまそ
4
一気読み。横並びからはずれるとパニクる、情報の受け手=自らの指示待ち族ぶりに自覚がない、日本の大衆。同、送り手=一方的な予定調和への迎合のためにジャーナリズムを棄てて恥じない日本の大手メディア。空気を読まず(ほめ言葉)、素直に生きる二人だからこそできた、異媒体職人の対談。この本が出て、わずか2年たらずの今、事態はもっと悪化している。2014/12/04
lily
3
気骨のある二人のジャーナリストによる対談集。メディアは市場原理を反映したポピュリズムに迎合したもの。ジャーナリズムは市場原理に左右されず真実を追求するもの。記者クラブの保守的な体制が報道の自由を妨げている。「にこにこ」と「にやにや」で印象はガラリと変わるのだ。大切なのはメディアは信じるものではないということ。なんでもかんでも鵜呑みにするのでなく、批判的・多角的な視点を持つことでリテラシーが育まれるのだろう。2016/02/24